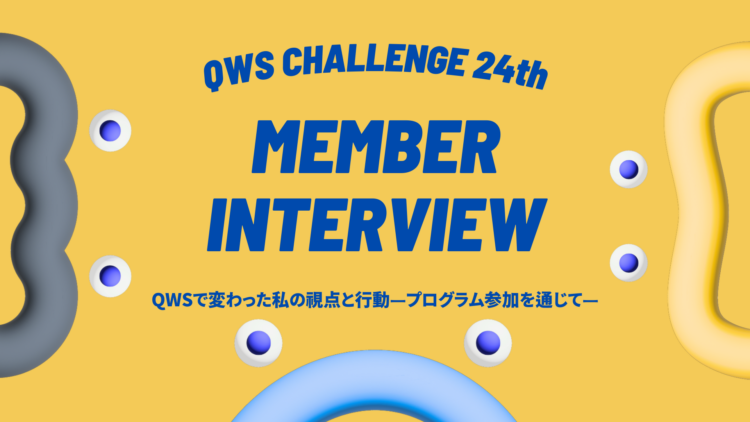3カ月間、問いと向き合い続けてきたプロジェクトメンバーたちの晴れ舞台、QWSステージ。今回は1月28日に開催されたQWSステージ#21の様子と、SHIBUYA QWS Innovation協議会(以下「SQI協議会」)による厳正な審査の結果、見事最優秀賞・優秀賞を受賞した5プロジェクトのSHIBUYA QWS(以下QWS)で見つけた価値や、次のQWSステージへ向けた意気込みをお届けします。
テキスト・編集=守屋 あゆ佳 写真=池原 瑠花・髙木 香純

QWSステージとは、3カ月に一度、QWSに集うプロジェクトメンバーがそれぞれの活動の中で見つけた「可能性の種」を放つ場です。QWSステージ当日はQWS内に舞台が設営され、発表するプロジェクトは、3分間で各々の活動成果についてピッチを行います。
QWSステージ#21では18プロジェクトが登壇し、各々の成果を発表しました。SQI協議会の審議のもと、全18プロジェクトの中から「micro development」がSQI協議会最優秀賞に選ばれました。また、SQI協議会優秀賞として「Kotoha」、「親子カルタ」、「MEMORI」、「comodo.」の4プロジェクトがそれぞれ受賞し、計5チームがQWSでの活動期間の延長の支援を受けることが決定いたしました。
キーノートトーク
QWSステージでは、各分野の第一線で活躍している方をゲストにお招きし、講演していただく「キーノートトーク」を実施しています。
今回のゲストは、東京大学大学院総合文化研究科教授の國分 功一郎さん。國分さんには哲学という観点から、ご自身の「問いへの向き合い方」をテーマにお話しいただきました。キーノートトークはページ下よりご覧ください。
登壇者略歴(國分 功一郎 氏)
東京大学大学院総合文化研究科教授
東京大学大学院総合文化研究科教授。専門は哲学・現代思想。主な著書に『スピノザ 読む人の肖像』(岩波新書、第11回河合隼雄学芸賞受賞)、『中動態の世界 意志と責任の考古学』(医学書院、第16回小林秀雄賞受賞)、『暇と退屈の倫理学』(新潮文庫)、『ドゥルーズの哲学原理』(岩波書店)、『スピノザの方法』(みすず書房)、『目的への抵抗―シリーズ哲学講話―』(新潮新書)、『来るべき民主主義 小平市都道328号線と近代政治哲学の諸問題』(幻冬舎新書)など。共著に『言語が消滅する前に』(幻冬舎新書)ほか。
プロジェクトインタビュー/micro development

micro development
双方の持続可能なまちの発展を小規模開発手法「マイクロディベロップメント」の概念から、渋谷とローカルの事業を構想するプロジェクト。今回は「ものがたりの力で不動産価値を上げられるか?」という問いを掲げ、新サービス「脚本不動産」を紹介。審査員からは小説コンテンツと不動産の掛け合わせが非常にユニークで、空き家課題の解決にも寄与しうる可能性を秘めている点が評価された。
受賞コメント
今回のQWSステージでは「物語×不動産」というアプローチが、地域の方、都市部の方、物件オーナーの3者に寄り添いながら「空き家問題」や「地域文化の衰退」の新たな解決の糸口になるという可能性を伝えられたらと思い、登壇しました。今回の登壇を通じて、改めて「問いを共有すること」の重要性を実感しました。ただ私たちだけがローカルで活動するのではなく、多くの人が「自分ごと」として関わることで、より大きなムーブメントになると感じています。
この3カ月間で印象的だったのは「脚本不動産」のローンチと、それに伴う地域との新たなつながりの広がりを感じられたこと。特に、これまで私たちが活動をしてきた東伊豆町をはじめとしたエリアで物件の魅力を「物語」として伝えることで、空き家や遊休不動産に対する関心が高まり、従来の不動産市場とは異なる新しい可能性が生まれました。
今後、「脚本不動産」は複数の地域で展開し、物件や地域のストーリーを多くの方に伝えていきます。さらに、渋谷とローカルを横断したプロジェクトを通して、多拠点での働き方・暮らし方の新たなモデルを推進していきたいと考えています。都市と地方が互いにポジティブに影響し合う社会の実現に向けて邁進します。
プロジェクトインタビュー/Kotoha

Kotoha
Kotohaは「消えゆく言語を守るためには?」という問いを掲げ、消滅の危機にある約3500もの「少数言語」と呼ばれる小さなことばたちを、映像を中心としたインスタレーションや展示、ネーミングビジネスの視点から後世に残すことに挑戦している。審査員からはリーダーの原体験から生まれた問いであることや、よりネーミングのアイデアが具体化することで、ビジネスシーンでの実用可能性に繋がるのではないかと期待が寄せられた。
受賞コメント
QWSでお世話になったコミュニティマネージャー、コミュニケーターの方々、そして何より3カ月一緒に走ってくれたメンバーのためになんとか賞を獲りたいという気持ちがあったので、2つもいただくことができて嬉しく、少しホッとしています。今回は多くの方に馴染みがないであろう言語問題の深刻さ、そして少数言語たちの面白さを伝えることを意識しました。この3カ月は苦しいこともありましたが、決して問いから逃げず、毎日食らいつきました。フィールドに出て問いと向き合い直した1カ月目、とにかくアイデアを磨いて実践した2カ月目。そして最後の1カ月は、QWS CROSSTAGEを通じて多くの方に私たちの活動に触れていただくことができました。やっと、プロジェクトとしてスタートラインに立てたような気がしています。
私の最終ゴールは、世界中、日本中のいろんな言語に囲まれながら死ぬことです。その目標を達成すべく、これからも少数言語たちと楽しく活動していきたいです。これだけ英語が重要視されるこの社会だからこそ、少数言語たちが持つコトバの力の可能性は無限大だと思っています。
プロジェクトインタビュー/親子カルタ

親子カルタ
「思春期の概念を察する親子のコミュニケーションとは?」という問いを掲げる親子カルタ。思春期の親子関係は避けられないものではなく、日常の接し方やコミュニケーションの工夫によって改善できるのではないかという視点から、親子間の対話を自然に生み出す工夫として、カードゲーム「親子カルタ」「こうしよう」を開発。 カードゲームからコミュニケーション課題を解決しようとする切り口が審査員からユニークだと好評を受けた。
受賞コメント
QWSステージで一番伝えたかったことは、「親子が共有し合える機会を増やすことの大切さ」。この3カ月間はふれあい館をはじめ、複数の場所で実証実験を行い、カードゲームの効果を検証しました。 さらに、QWSで活動する『まなびぱれっと』との合同イベントを開催し、他の家庭と協力しながらゲームを進めていく中で、親子間の対話の拡大の可能性も検証しました。結果、カードゲームのコミュニケーションへの価値や可能性を確かめることができました。
今回、優秀賞を受賞できたことはとても嬉しいです。また審査員や関係者の方々からフィードバックや評価をいただき、プロジェクトの方向性に対して自信が強まりました。 次の3カ月ではカードゲームのさらなる改良や、新しい実証実験の実施、プロジェクトの価値を多くの人に届けるための活動を進めていきたいと考えています。また、少し先にはなるかもしれませんが、企業や地域コミュニティ、教育機関、医療機関との連携も強化していきたいです。企業のCSR活動や家庭学習ツールとして、カウンセラーや心理士などの専門家による支援、また学校や児童育成館などへの活用も視野に入れて、アップデートを検討していきます。
プロジェクトインタビュー/MEMORI

MEMORI
MEMORIは、忌避されることの多い「別れ」や「死」と向き合うことで、今をよりよく生きるためのきっかけを創出するプロジェクト。家族や友人、恋人や恩人、大切な人たちとの繋がりを再確認し、それぞれへの思いを『ラストレター』として未来に遺す文化が社会に広がることを目指している。審査員からは「死」をなんとか自分ごととして捉えてもらうためにも、災害シーンなどとの連携について今後の期待が寄せられた。
受賞コメント
今回のQWSステージの目的は明確で、MEMORIを通じて「こんな文化を創っていく」という宣言と、そのために企業・地方自治体のみなさんとご一緒したいという提案でした。この3カ月を振り返ってターニングポイントとなったのが、前回、企業賞をいただいたセブン-イレブン・ジャパン様とのディスカッションと、CROSSTAGEへの出展でした。これまで私たちは「死」というテーマの特性上、無意識に巻き込む範囲を身近な人たちに閉じてしまっていたことを実感。CROSSTAGEで多くの方にご意見をいただけたこと、セブン-イレブン・ジャパン様の社会や地域、お客様への姿勢に示唆を得たことで、MEMORIの取り組みを、社会に向けて発信をしていく覚悟が決まりました。
ピッチで話した「正式版アプリのリリース」と「法人設立」は、MEMORIの目指す世界に向けてのあくまで手段です。ただ、同時に大きな節目にもなると感じています。これから企業・自治体のみなさんと協業していく中で、MEMORIに込めた思想性を大切にしながらも、持続性のある取り組みに進化させられるよう、頑張ります!
プロジェクトインタビュー/comodo.
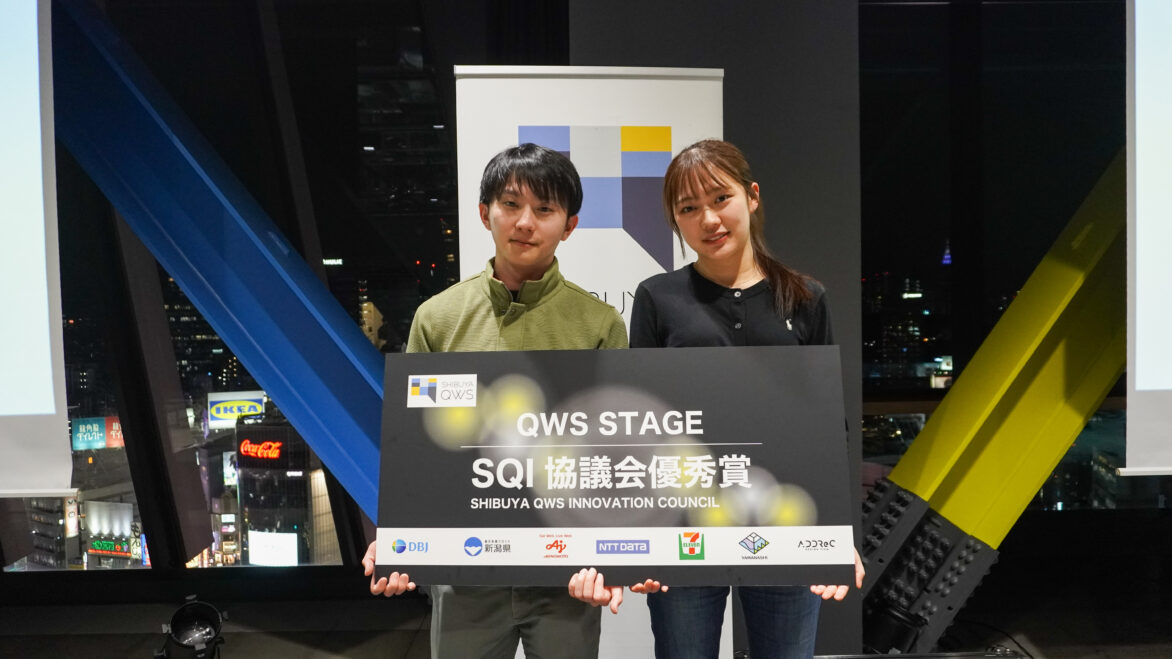
comodo.
QWSチャレンジ19期生として入会以降、「両親の関係性が子どもに与える影響はどれだけ大きいのか」という問いに向き合うcomodo.。両親の関係性は小児科学的にも子どもの将来に与える影響があることから、新たなアプローチとして、パパが育児を学ぶ場『Papa voyage』を考案し、現在実証実験に取り組んでいます。審査員からは男性の育児参画という社会課題への鋭いアプローチや、プロジェクトが着実に進んでいる点が評価された。
受賞コメント
これまで多くのママパパに話を聞いてきましたが、ママたちが口を揃えて一番辛かったと話すのは「産後の孤独感」。これを解決するために産後ケア施設など、最近はママのためのサービスは増えてきています。女性の社会進出や男性の育児参画が社会で進められる一方で、男性が育児に関わるための支援が全く足りていないと考えます。そこで、ママの一番身近な存在であるパパにも着目する必要があると考え『Papa voyage』を立ち上げました。この3カ月では、菊池医院(福島県郡山市)での実証実験が開始。小児科クリニックでの実証実験を開始したことで内容も充実、実際に看護師さんや小児科医からのフィードバックをもらうこともでき、今後の展望も見えてきました。私たちのプロジェクトは通常のスタートアップとは異なり、初速に時間のかかるもの。ただ、これまでにないサービスを作り上げるためには、時間はかかっても地道に実証実験の回数を重ねて改良していくことが必要だと考えています。
comodo.はこれからも育児を「やらなきゃ」から「やりたい」と思えるものにすべく、親御さんのサポートに全力を尽くしていきたいと考えています。そして、子どもたちがすこやかに育つことのできる社会がつくられ、その子どもたちが次の時代に親となることで、時代を超えて連鎖していくことを願っています。
QWSステージ#21登壇プロジェクト一覧
1. LaMuse|生成AIを活用して、個々人の背景やストーリーを反映した個性的なファッションをどのように実現し、自己表現の新しい形を創造できるか?
(18:30~18:34頃)
2. Kotoha|消えゆく言語を守るためには?
(18:34~18:38頃)
3. MEMORI| 自分の死は「誰に」「どうやって」伝わるのだろうか?
(18:38~18:42頃)
4. 村人A|どうしたら中高生の物語を未来の価値として紡いでいけるか?
(18:42~18:46頃)
5. マイノリティ研究所 マイノリティ研究促進プログラム|障害における課題を解決する上で、多様な視点を効果的に取り入れる方法は?
(18:46~18:50頃)
6. micro development| ものがたりの力で不動産価値を上げることはできるのか?
(18:50~18:54頃)
7. 小さな美術館|好きなことを好きで居続けることはどうしてこんなに難しいのか?
(18:54~18:58頃)
8. もふもふ教育革命|もふもふは、学びをどのように変えるのか?
(18:58~19:02頃)
9. プロジェクト備考欄|取るに足らない“ワタクシゴト”と、いかにして戯れることができるのだろうか?
(19:02~19:06頃)
休憩(約10分)
10. 蛸みこし ∞ ePi Art|〈蛸みこし〉は、タコー感を醸成するのか?
(19:16~19:20頃)
11. 東京外国語大学Web・SNS研究会|SNSによって「世界」は本当に広がったのか?
(19:20~19:24頃)
12. MBTI X DESIGN|デザインが顧客の性格を理解し、今の自分とは違う別の性格への進化を導くためには?
(19:24~19:28頃)
13. Bullyless World|発達障がい者に理解ある社会を築くには?
(19:28~19:32頃)
14. 親子カルタ|思春期の概念を崩す親子のコミュニケーションとは?
(19:32~19:36頃)
15. n拠点|拠点があることによって生まれる価値とは?
(19:36~19:40頃)
16. cutism|可愛くなりたい女の子がルッキズムを理想論ではなく現実的に解決するには?
(19:40~19:44頃)
17. ビヘイビアプロジェクト|私たちは自分たちのふるまいを、自らの意思で変えることができるのか?
(19:44~19:48頃)
18. comodo.|両親の関係性が子どもに与える影響はどれだけ大きいのか?
(19:48~19:52頃)
「未知の価値に挑戦するプロジェクト」を募集しています
2025年2月から活動を開始したQWSチャレンジ第22期のメンバーは、年齢も領域も様々。新しい仲間、新しい自分、新しい世界。どんな出会いが待っているのでしょう。それぞれのプロジェクトの問いは、どのように磨かれ、放たれていくのでしょうか。次回のQWSステージ#22は、2025年4月末に行われます。QWSから生まれる「可能性の種」をお楽しみに。
現在、QWSチャレンジ第23期を募集しています。詳しくはこちらをご覧ください。