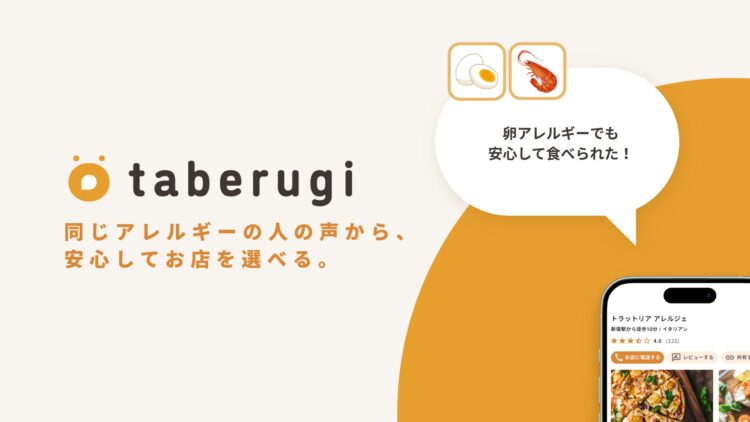夢を持って目標に突き進む子供たちを増やすのに最適な教育プログラムとは何か❓✨
何にチャレンジするのか?
私たち学生団体Educereは、「個性を伸ばし、個性を活かす教育」の実現を理念に活動している。その根底にあるのは、夢を持って目標に突き進む子供たちを増やしたいという強い信念だ。私たちの団体のメンバーは、ビジネス、政治、音楽、スポーツサイエンスなど、それぞれ異なる分野で夢を描き活動している。しかし、共通するのは、自らの熱意に従い挑戦することに生きがいを感じ、それをもっと多くの若者にも広げたいという思いである。近年、総合型選抜の拡大などを皮切りに、大学や社会では多様な夢や能力を評価する傾向が強まっている。一方で、小中学校の教育ではこうした流れが十分に反映されておらず、そこに課題を感じている。そこで、私たちは現在、中学校とコラボしながら、自己分析ワークショップなど実践型プログラムを開催し、「どのようなプログラムが最も効果的に子供達に夢を持たせ、活動を促せるのか」という問いに日々向き合っている。QWSでの活動などを通じて、我々の中でその最適解を見出し、最終的には市区町村への陳情という形でその答えを社会に共有していきたい。
Instagram:https://www.instagram.com/educere.0810/
なぜチャレンジするのか?
私たちは、この問いを通じて、「すべての子どもが自分の夢を描き、夢に向かって挑戦できる社会」の実現を目指している。現在、未だに多くの生徒が従来の一律的な学歴社会の評価基準に縛られ、自分の可能性に気づかないまま進路を選択し、自己肯定感を失うケースが少なくない。一方、私たちのプログラムは、子どもたちが自らの興味・関心を理解し、それに基づいた学びや経験を積める環境を促進する。これは個々の生きがいにつながるだけでなく、多様な能力を評価しようとする社会の流れを加速させ、その効果を最大化させる可能性を秘めている。具体的には、それぞれがパッションを見つけることで、個々のインセンティブと生産性を向上させ、大学や会社とのミスマッチを減らし、社会全体のwell-beingを促進できると考えている。また、AIが当たり前になりつつある世の中、物質的豊かさから精神的豊かさへ注目が移行してる世の中において必要なのは、多様な夢を描く多様な人材であるはずだ。
どのようにチャレンジするのか?
まず、QWSでは我々の問いを共有し、私たちが行ってるプログラムの精度を向上させたい。QWSには大学教授、社会人、大学生、高校生がいるため、彼らに「大学入学前にどのような経験を積むべきか」「社会ではどのような基準で評価されるのか」「一般受験と総合型選抜で入学した学生の違い」「小中学生の頃にどのようなプログラムがあればよかったか」などの質問をすることで、様々な意見を集め、その視点を我々の活動に活用させる。また、QWSには多様な分野で挑戦する高校生や大学生が集まっている。そのため、彼らに「その分野に興味を持ったきっかけ」や「最初に取るべき行動」をヒアリングし、PDFにまとめる予定だ。現段階では、私たちがコラボ先の中学生たちに提案できる具体的なファーストアクションは、どうしても我々の得意分野に寄りがちだ。そこで、そのPDFをコラボ先の学校に配布することで、生徒それぞれの興味に合った活動を促進できるのではないかと考えている。

石川 輝
石川 輝
N高等学校9期生。芸術活動家として、世界の人権問題を訴える楽曲制作に取り組んでおり、世界人権デーに投稿した「1人にはしない」は総再生回数1万回を突破。また、防災を広める学生団体Aceboraと、個性を活かす教育を実現する学生団体Educereを立ち上げ、代表を務める。トビタテ留学JAPAN8期生。Makers University U-18 10期生。

狩野 元気

小川 茉穂
小川 茉穂
高校1年で「トビタテ!留学JAPAN」に選ばれ、NYでボーカル留学。AX発声法を学び、ライブや作詞作曲、SNSで音楽を発信。JAZZ・HIPHOP・バトントワーリングで表現力を磨く。スタンフォード大学の講座で“自分らしい生き方”を探求。学校では企画・運営にも関わる。通信制高校への偏見をなくすため、株式会社プレマシードでインターン中!
採択者コメント

ぜひEducereの考える「個性を伸ばし、個性を活かす教育」とはどんなものなのか?を突き詰めて欲しいです!現役高校生だからこそわかる課題とその解決策に、かつて高校生だった現役大人達も期待しています。
連続起業家・エンジェル投資家松村 映子
リーダーインタビュー
あなたの[問い]は、どのような未知の価値に繋がると考えますか?
私たちは、この問いを通じて、「すべての子どもが自分の夢を描き、夢に向かって挑戦できる社会」の実現を目指している。現在、未だに多くの生徒が従来の一律的な学歴社会の評価基準に縛られ、自分の可能性に気づかないまま進路を選択し、自己肯定感を失うケースが少なくない。一方、私たちのプログラムは、子どもたちが自らの興味・関心を理解し、それに基づいた学びや経験を積める環境を促進する。これは個々の生きがいにつながるだけでなく、多様な能力を評価しようとする社会の流れを加速させ、その効果を最大化させる可能性を秘めている。具体的には、それぞれがパッションを見つけることで、個々のインセンティブと生産性を向上させ、大学や会社とのミスマッチを減らし、社会全体のwell-beingを促進できると考えている。また、AIが当たり前になりつつある世の中、物質的豊かさから精神的豊かさへ注目が移行してる世の中において必要なのは、多様な夢を描く多様な人材であるはずだ。
あなたの「問いの感性」は、どのような経験を通じて育まれましたか?
私が中学3年生の時、受験が近づくにつれ、日本の一律的な教育や学歴社会に違和感を覚えた。そこで区の英語スピーチコンテストに学校代表として出場し、「Learning to be yourself」というテーマで「学びとは本来自分のためにあるのではないか」と訴え、2位を獲得した。その後、「生徒とともに学校を創りたい」という理念を掲げるとある高校にワクワクしながら1期生として入学。しかし、実際には膨大な学習量を課せられ、従来の学歴社会の枠を超えない学校であることに失望した。そんな中、『実力も運のうち』という本と出会い、学歴や学力は単なる指標の一つでしかないと気づいた。同時に総合型選抜の存在を知り、その可能性に惹かれて、その入試方式での大学受験を目指すようになった。そして高校2年から通信制高校に転校し、政治・近代史・経済・哲学を本格的に学びながら、世界の人権問題を訴える楽曲制作などの課外活動にも取り組んだ。その結果、日々の学びに大きな充実感を感じるようになった。また、日本の教育に疑問を抱いてるだけでなく、自分と同様に課外活動に取り組む仲間たちを集め、学生団体Educereを設立。この団体では、清泉女子大学の入試顧問や文京区教育長へのヒアリングを通じ、総合型選抜が大学や行政でも注目されているのを知った一方、多様な人材を評価しようと試みる社会の流れが小中学校のカリキュラムには十分に反映されていないと感じた。加えて、自分自身も「もっと早くから自己分析や課外活動について知る機会があれば」と強く思った。そこで現在は中学校と連携し、実際に自己分析ワークショップを開催しながら「どうすればより多くの子供たちが夢を持ち、目標に向かって挑戦できるか」という問いを探求し続けている。
QWSステージでの発表
新着プロジェクト New Project

QWS チャレンジ
はじめてみませんか?
進めることができる内容であれば、分野や規模に制限はありません。
ぜひ、プロジェクトの更なる可能性を試してみませんか。
プロジェクトベースが
無料で利用可能!