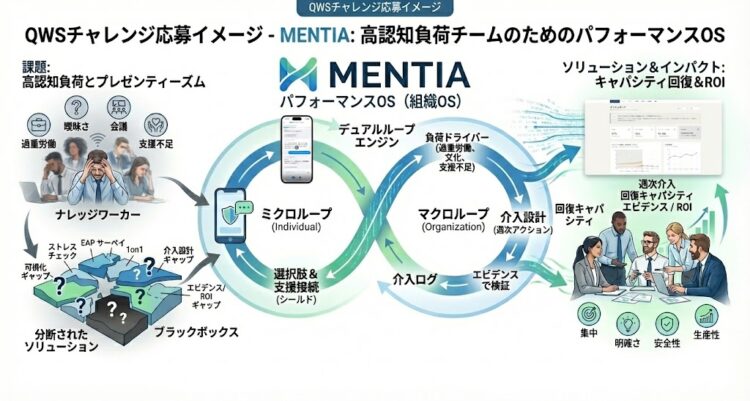“I’m fine, Thank you” に代替する、スポーツを用いた言語習得は可能なのか?
何にチャレンジするのか?
QWSでは、多様なアクターが継続的に関わり合えるコミュニティや空間の創出が可能かどうかを検討したい。また、自治体・企業・大学にとって、GloBusと関わることにどのようなメリットがあるのかを探っていく。
今後活動を持続可能なものにしていくには、運営にかかるラーニングコストを考慮し、どのようにマネタイズしていくか、あるいは非営利の形で関わるのかという方向性の検討も必要である。
スポーツを切り口に、相互に関わり続けられるコミュニティのあり方を模索することで、他の領域にも応用できる持続的な場づくりが可能になると考える。
さらに、自治体や大使館との連携を深め、GloBusがその橋渡しの役割を担うことで、地域の活性化にも貢献できる可能性がある。

なぜチャレンジするのか?
外国人労働者の増加が進む現代の日本において、第二言語の習得はもはや不可欠だと言っても過言ではない。しかし、日本の英語教育は実践からかけ離れており、多くの学生が英語を学ぶ意義を見出せずにいる。私はこの現状を打破するために、好きなことを通して英語を使う実体験を提供することが、これからの日本人にとって最も重要な教育だと考え、「GloBus」というプロジェクトに挑戦してきた。
GloBusでは、バスケットボールを通じた非言語的コミュニケーションを起点に、英語への心理的ハードルを下げ、第二言語習得や多文化理解へのきっかけを提供してきた。実際に参加者が、英語を好きになったり、短期留学に参加したりするなど、手応えはあったものの、高校生だけでの運営には限界があった。特に継続性や参加者にとっての適度な緊張感の確保に課題を感じている。
だからこそ、GloBusの次のフェーズには、自治体・企業・大学など多様なアクターが継続的に関われる仕組みが必要だと考える。QWSは、異なる立場の人々が関わり合い、共に模索し続けられる場であり、私たちはその環境を活用しながら、より持続可能で社会に根ざした言語習得の形を追求していきたい。

どのようにチャレンジするのか?
GloBusの活動に共感してくれる自治体・企業・大学の担当者や団体と、QWSを通じて対話と協働の機会をつくりたい。参加者の英語力向上に加え、地域イベントや学校との連携、大使館との交流など、社会に開かれた形での展開を模索する。
将来的には、GloBusを通して出会った若者たちが、多様な立場の大人と継続的に関われる仕組みを構築し、共に言語と文化を学び合う場を創っていくを目指す。

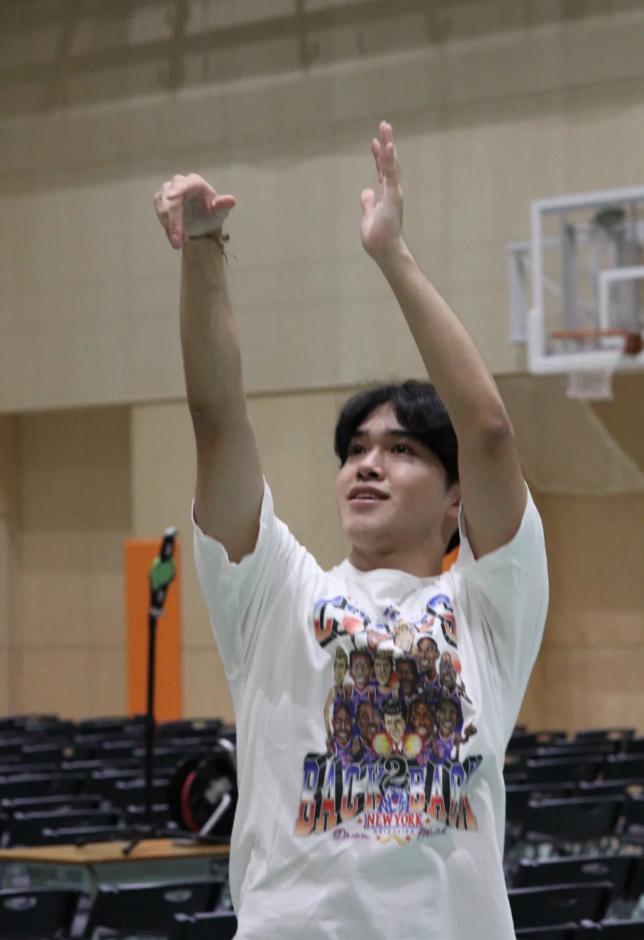
名執有貴

サイエドメリク
採択者からのコメント

リーダーインタビュー
あなたの[問い]は、どのような未知の価値に繋がると考えますか?
VUCAの時代において、母国語以外の言語を学ぶことの意味が問われる一方で、国内人口の減少に伴い、国内市場は縮小している。実際、中小企業の約8割が海外市場に進出しており、ただ翻訳できるだけではなく、文化的背景や現地のリアリティを理解する力が必要とされている。つまり、日本語だけで完結する世界ではもはや不十分だ。また、紛争や格差が増大する現代において、他者の国や歴史、文化を知ることは対立の根源を理解するために不可欠であり、そのための共通語として英語が重要になる。
しかし、日本人の多くは、格差や対立が少ない「当たり前」の中で育ち、そうした問題に対して当事者意識を持ちづらい。だからこそ、世界のあらゆる他者の現実を知り、自らの立場を相対化することが、異なる価値観とつながる第一歩となる。
そこで私は、外国人との親和性も高く、国籍、人種、言語、経済、性別、その全ての垣根を超えて人と人が繋がることができるスポーツという非言語的アプローチに着眼した。これにより、反射的に言語習得を促進するだけでなく、外国人と共に生きるとはどういうことかを、情動的に学ぶきっかけとなる。
だからこそ私は、スポーツを通じて外国人とつながり、言語を習得することで、外務省が掲げる「世界で活躍する人材の育成」だけでなく、より根源的なレベルで「なぜ世界に対立が生まれるのか」「異なる他者とどう共に生きるのか」といった問いに向き合う力を育てたいと考えている。言語は単なる道具ではなく、他者の視点を想像し、自らの当たり前を問い直すきっかけとなる。そしてそれは、今後多様化していく日本社会の中で、外国人労働者や異なる文化的背景をもつ人々と共に生きるための、土台となる感受性や理解力を育むことにもつながっていくと信じている。
あなたの「問いの感性」は、どのような経験を通じて育まれましたか?
幼稚園から中学校までインターナショナルスクールで過ごした私は、日本の私立高校に転校した際、日本の英語力の低さに強い衝撃を受けた。インターでは、日常的にさまざまな言語が飛び交い、異なる価値観や文化に自然と触れていたからこそ、そのギャップはとても大きく感じられた。さらに、シリコンバレーを訪れた際には、世界中から集まった多様な人々が、互いに異なる言語や背景を持ちながらも協働し、社会を動かしている様子を目の当たりにした。言葉の壁を越えて人とつながる力が、今の世界にとっていかに重要かを実感した経験だった。
そのような中でリサーチを進めると、文部科学省は「2050年頃には、多文化・多言語・多民族の人々が協働する国際的な環境が当たり前となる」とし、「外国語を用いたコミュニケーションの機会を段階的に増やす必要がある」と明記していた。こうした将来の理想と、現在の日本の教育現場とのあいだには大きなギャップが存在していると感じた。
その後、英語が話せる生徒の多くが、第一言語として英語に親しんできた環境にいたことにも注目し、日本の状況をより客観的に捉えるために、英語を母語としない「韓国」との比較を行った。EF English Proficiency Index 2024によると、日本は116か国中92位、韓国は49位。TOEFL iBT 2023では、日本の平均スコアが73点に対し、韓国は86点、世界平均は88点と、日本の英語力の低さが数値としても明らかになっている。
日本の中高では合計約670時間(約915コマ)の英語授業を受けているにもかかわらず、実際には英語力が出ていない。一方、韓国の総授業時間は約595時間(約743コマ)と少ないが、会話型やオンライン英会話など校外での実践機会が豊富である。この差から、「時間」ではなく「実践環境と心理的ハードル」が課題だと仮説を立てた。
検証のために、学校の生徒に意識調査を実施したところ、「英語を話したいけど楽しくない」「使う機会がない」「恥ずかしい」といった声が多く、心理的ハードルの高さが明らかになった。また、「授業は先生がずっと話しているだけで実践的じゃない」「一方的に聞くだけでよく分からないし、つまらない」といった声も多く、学習内容が体感的でないことが英語への苦手意識をさらに強めていることがわかった。
このような受け身の授業では、生徒が自ら関わろうとする動機が生まれにくく、結果として学習の進度や関心も低下してしまう。だからこそ、英語を「聞くだけ・訳すだけ」ではなく、自分の体で体験しながら学べるような、もっと能動的に関われる空間が必要だと考えるようになった。
そして、日本人が英語に対して抱えがちな言葉の壁を越えるためには、あえて「言語」とは逆の非言語的アプローチに着目した。
新着プロジェクト New Project

QWS チャレンジ
はじめてみませんか?
進めることができる内容であれば、分野や規模に制限はありません。
ぜひ、プロジェクトの更なる可能性を試してみませんか。
プロジェクトベースが
無料で利用可能!