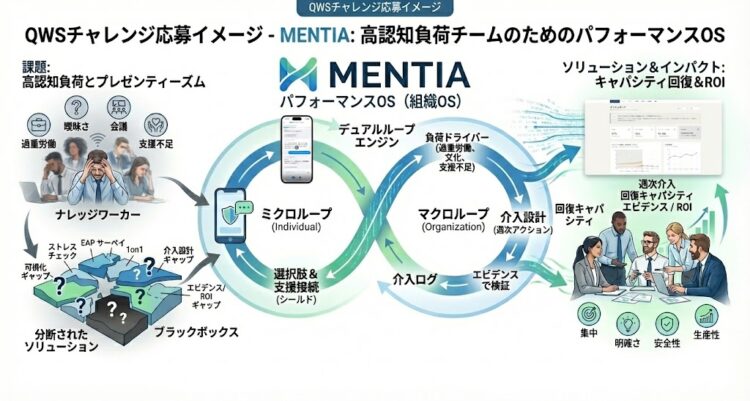もし自治体が公募をする際に、“前年踏襲”のような慣習ではなく、ゼロベースで最適な企業を選ぶ仕組みになったら、社会はどう変わるか?
地方自治体と企業・団体のマッチングを促進し、【より税金の活用の仕方として、効果的な、費用対効果が高い】官民連携(PPP: Public-Private Partnership)を実現する。
●背景
・行政の課題や政策に関する情報が分散しており、企業が適切な機会を見つけにくい。そのため、営業の受注率が1%を切るというくらい低い
・民間企業は、行政が提示している総合計画、個別計画、行政課題の一覧化リストを見つけられない。把握できていない。
・官民連携のプロジェクトが形式的になりがちで、効果的なマッチングが不足している。
●ソリューション:
・AI × Webクローリング技術を活用し、全国の自治体が発信する【総合計画、課題一覧のリスト、公募情報】を一括検索できるプラットフォームを提供。
・企業のサービスと自治体の課題を自動でマッチングし、適切なアプローチを支援。
・最終ゴール:住民が自らの意見をDirectに行政に伝えることが可能な、行政と住民の意見交換プラットフォームを構築し、より実効性のある官民連携を推進。
●ミッション 住民の声が、ダイレクトに"行政"に届く世の中へ
何にチャレンジするのか?
自治体が公募を行う場面で、入札やプロポーサル案件の落札は、一般的には、“前年踏襲”のような慣習が根強いが
行政(市区町村)が抱えている課題を解決する一手として、過去に市区町村から発注経験がない「スタートアップ企業や中小企業」まで、発注先の選択肢を広げることにチャレンジします。そして、最終的には、発注先企業を決める”プロセス”において住民が、関与することができる仕組みを作ります。

なぜチャレンジするのか?
(内閣府の世論調査より)「住民の意見が反映されていない」という回答が約7割を占めているこの国、日本において、住民の課題や意見をより一層、直接的に行政に届ける世の中を創ることで、最終的に『将来に期待や希望を描ける日本』を創る。
どのようにチャレンジするのか?
各市区町村が公開している「行政課題のリスト」に対して、過去に発注経験がない民間企業が解決の担い手となることで、官民連携スキームを促進する
最終的には、行政課題解決に向けて応募する民間企業の情報をオープンにすることで、在住の市民が、課題解決を担ってほしい民間企業に対して一票を投じて投票できるような仕組みを構築する
採択者コメント

Biz+が花開くことで、日本の自治体DXが進化することを応援します。
リーダーインタビュー
あなたの[問い]は、どのような未知の価値に繋がると考えますか?
市区町村が民間企業に仕事を発注する場面において、
●過去の受注経験ありきの“前年踏襲”のような慣習ではなく、ゼロベースで最適な企業を選ぶ仕組み
かつ
●(最終的には、市区町村が発注先の企業を決めるが)発注先企業を決める”プロセス”において住民が、関与することができる仕組み
この両輪を構築することで
住民の課題や意見をより一層、直接的に行政に届ける世の中になる。
さらに、最終的には『将来に期待や希望を描ける日本』を創ります。
あなたの「問いの感性」は、どのような経験を通じて育まれましたか?
大学時代のゼミ活動において、社会課題の解決に向けた、非営利組織などのビジネスモデルの研究を行っていました。社会人になってからは、より一層の『公的資金(税金など)の使い道や効果』について、疑問を抱くようになりました。民間企業では、予算の使い方を検討する際にROI(投資対効果)が意思決定の重要な基準となります。その一方で、行政においては、公的資金(税金など)の用途が、民間企業と比較すると、それほど厳密に検討されていないのではないかと考えています。
例えば、M市では街の活性化を目的とし、前年踏襲で、とある民間企業にアプリ構築費用として多額の予算が投入されましたが、2年後の利用実績はわずか2名という結果でした。同様の事例が、複数市で発生しているのを目の当たりにしています。
このような事例を通じて、公的資金(税金など)の使い方について、従来よりもさらに一層、費用対効果を考慮した活用方法を模索できるのではないか?、より効果的な活用方法があるのではないか?、という問いが生まれました。
QWSステージでの発表
新着プロジェクト New Project

QWS チャレンジ
はじめてみませんか?
進めることができる内容であれば、分野や規模に制限はありません。
ぜひ、プロジェクトの更なる可能性を試してみませんか。
プロジェクトベースが
無料で利用可能!