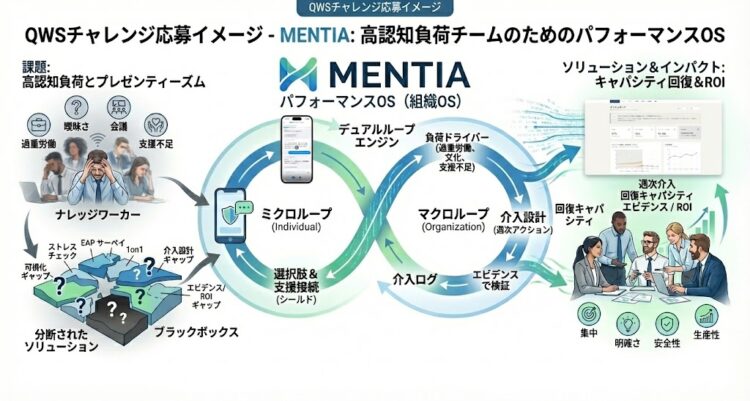繋がる時代にぼくらが持ちたい「倫理」ってなんだ?
何にチャレンジするのか?
繋がりあう社会の中で持っていたい倫理観とは何かを考え、発信を通じて人々の倫理観をアップデートすることをめざします。

なぜチャレンジするのか?
ぼくらは「倫理観」とは個人が物事を理解し行動を行う上での判断基準と考えてます。
想像力をもちながら倫理観を知る機会があることで、押し付け合うような説得ではなく、互いに理解し合う対話が生まれ、新たな選択肢を生むキッカケになるのではないかと思っています。
そうして生まれた選択肢は、これまでの課題解決では救う事ができなかった課題を救うことに繋がり、ニッチながらも強いファンを持つものになるのでは無いかと信じています。
どのようにチャレンジするのか?
一人ひとりが自身の倫理観を理解するため、倫理的活動とその背景にある倫理観を紐解き構造化した「ぼく倫チャート」を開発し、SNSを使って発信していきます。
現在、プロトタイプとして#1をTwitterで発信しました。その結果、発信する上での立場を明確にすべきなど、多くの課題が見えてきたので、今後#2以降の発信活動を通じて、より多くの人へ自身の倫理観について考えるきっかけを提供できるコンテンツの制作をめざします。
プロジェクトメンバー

高田将吾

吉備友理恵

竹本建太

井口香穂

河田あさな
河田あさな
BtoBプロダクトのPjMを務める傍ら、地域の魅力や社会問題を伝える企画を行っています。みんなが作法をもって生きる世の中をつくりたい。

横山明日香
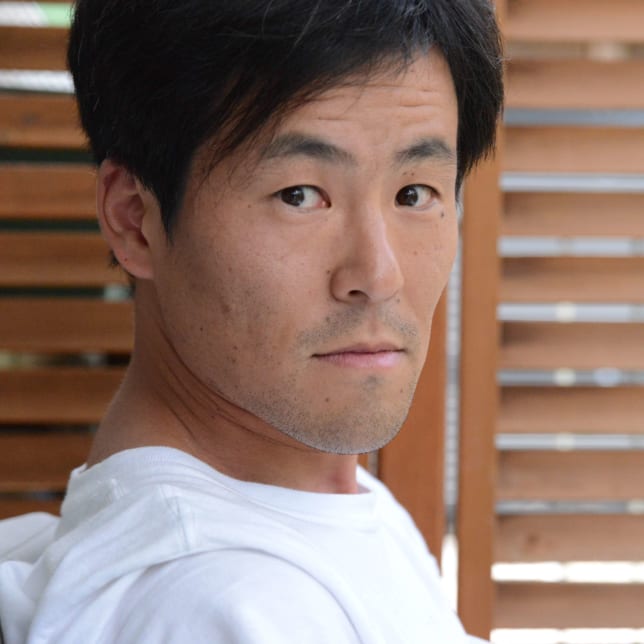
高見祐介

鈴木かのん
鈴木かのん
UIUXデザイナー。視点をまるっと変えた時の驚きと発見を表現したくて、立体からデジタルまでいろいろ試している。趣味はカメラと寺社仏閣をめぐること。

山根聡太郎
山根聡太郎
プログラミングに人間性は介在しないと気付いてエンジニアを辞めたフリーランサー。質の良い教育をみんなに提供するイベント主催したりしている。
応援コメント


リーダーインタビュー
あなたの[問い]は、どのような未知の価値に繋がると考えますか?
倫理を理解することは、多くの人から共感を得るプロジェクトの立ち上げに繋がります。 アイデアがコモディティ化していく現代において、顧客の声に耳を傾けるだけでは、顧客の潜在的なニーズを捉えることはできません。 顧客からではなく、自分自身の価値観=倫理観からプロジェクトを始める事で、マーケティングリサーチなどでは捉えきれない、小さな兆しを捉えることができます。
そうした兆しをもとに、プロジェクトを立ち上げていくことは、顧客がこれまで気づいてこなかったような潜在的なニーズに訴えることができ、共感を集めるプロジェクトの立ち上げに役立つのでは無いかと考えています。 また、持続可能性というキーワードが注目を集める現代社会において、社会課題を倫理的に解決していくことは、社会課題を自分ごとに感じている顧客の自己実現を支えることに繋がり、結果として企業の成功に貢献します。
あなたの「問いの感性」は、どのような経験を通じて育まれましたか?
新規事業を考えている中で、自分が魅力に感じる事業は、大きな社会課題に対して自分自身の倫理観を基に選択肢を作り出している人々の活動でした。
ビーガンだった女性は、自分が食肉に対して嫌悪感を感じるのは、肉を食べることではなく工場生産された肉を食べることだということに、自身の倫理観と向き合うことで気がつきました。 その結果、自分が肉を食べないという選択肢を取るだけでは、市場に変化を起こすことができないと考え、自らが肉屋として工場生産されていない、彼女の視点から見てエシカルに感じる肉屋を開業しました。
それは、これまで、二者択一だった食肉の市場に新たな選択肢を立ち上げ、同じような倫理観を持つ人々から共感を集める事業になると思います。
こうした取り組みが、食肉だけでなく様々な社会課題を抱える市場において多発することを促すことができれば、より早く多くの人にとって気持ちいい社会が実現するのではないかと考え、そのためにも倫理観をアップデートする必要性を感じました。
QWSステージでの発表
新着プロジェクト New Project

QWS チャレンジ
はじめてみませんか?
進めることができる内容であれば、分野や規模に制限はありません。
ぜひ、プロジェクトの更なる可能性を試してみませんか。
プロジェクトベースが
無料で利用可能!