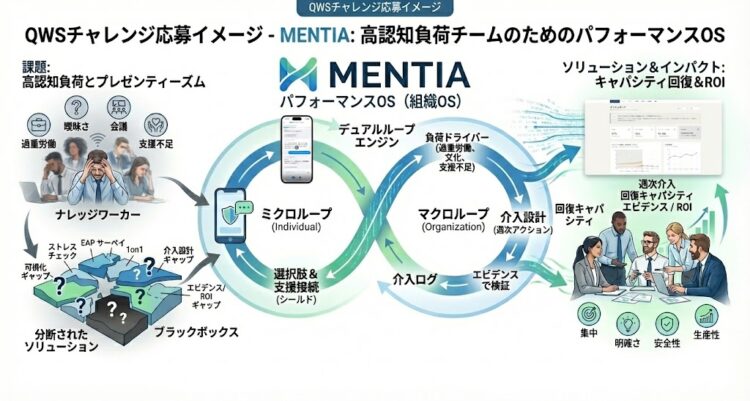どうすれば日本が図解先進国になれるだろうか
図解にはあらゆるモノゴトを多視点から構造化して可視化することができる力があります。1,000の言葉よりも、1枚の図の価値を信じてみる。
私たちは図解の力を社会実装し、複雑な課題の解決に挑戦します。「脱・言語中心主義」にシフトする世界を見据え、図解を単なるビジネススキルとしてだけでなく、日本人の新たなアイデンティティとなる思想として定義しています。現代哲学・認知科学・日本文化論をベースとして、図解が日本の経済・教育・文化を再興する社会を実現します。
何にチャレンジするのか?
図解スキルの可視化と普及
なぜチャレンジするのか?
日本を図解先進国にするため
どのようにチャレンジするのか?
仲間や協力者と出会う
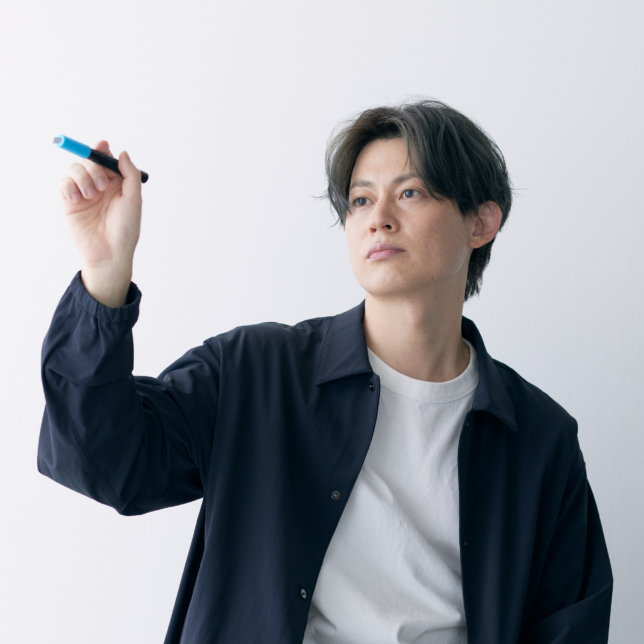
髙野雄一
髙野雄一
1989年生まれ栃木県出身。 東京理科大学オープンカレッジ講師。 あらゆるモノゴトを図解で多視点から構造化して可視化する図解起業家。 高卒で自動車工場で働くキャリアからスタート。独学で勉強しながら学費を貯めて東京理科大学へ入学。2015年に富士通マーケティング(現:富士通Japan)へ入社後、営業を経てDXコンサルティング部署の立ち上げに従事。 社会人学生として慶應義塾大学大学院SDM研究科を修了し、図解に関する論文を執筆。図解を用いた思考法『ダイアグラム思考』を創案。提供する講演・研修プログラムはキャンセル待ちが出るほど注目度が高く、参加者数は延べ1万人を超えている。

桑島健一
桑島健一
東京農業大学卒業。 製薬会社MR、ヘルスケアスタートアップベンチャーを経て、Metagramでシニアマネージャーを務める。 医療業界や自治体における現場課題の抽出、構造化したうえでのソリューション提案に従事。 図解のバリュープロポジションの明確化と同時に認知拡大、共感醸成を図る。

古敷谷あゆみ
古敷谷あゆみ
女子美術大学卒業。 DTPデザインやグラフィックデザインを得意とし、図解を視覚的に効果を高めるためのクリエイティブディレクターを務める。
採択者からのコメント

大学院環境情報学研究科都市生活学専攻(博士後期課程・博士前期課程)/都市生活学部西山 敏樹
リーダーインタビュー
あなたの[問い]は、どのような未知の価値に繋がると考えますか?
日本人が図解というツールを用いて使いこなすことができるようになれば、世界をリードすることができる人材の育成、文化の再発見・保存など、多岐に渡って日本が世界に対してのアイデンティティを確立することができます。 具体的な事例を1つ紹介します。 大手メーカーでソフトウェア設計をしている高橋さん。2年ほど前に戦略策定リーダーを任されました。しかし、リーダーというポジションの壁にぶつかり、日々悩んでいました。そんな時に出会った「ダイアグラム思考」で見事に壁を突破し、リーダーとしての職務を楽しめるようにまで成長できました。 最初は頑張って作成した中期計画のドキュメントを上司に持っていくと、「ポカーン」とされてしまったとのこと。さらに、上司からもらうフィードバックもいまいちピンとこず、エネルギーを投入しても、成長を実感できない時期が続きました。 そんな時に出会ったのが「ダイアグラム思考」でした。まず、大きな変化があったのがアウトプットが加速したことです。それまでは1週間に1枚程度の戦略アイデアしか作れなかったのですが、ダイアグラム思考を使い始めてからは1日に2~3枚のアイデアを出せるようになりました。 さらに、図を描くことで自分の意見が無駄なくスッキリしていったとのこと。本当に伝わるドキュメントが作れるようになることができるようになりました。 このように図解は次世代リーダーに必要なスキルを短時間で身に着けることができます。 本事例を人単位から企業単位へ、そして国単位へスケールすることで、図解が与える恩恵を最大化することができると考えています。
あなたの「問いの感性」は、どのような経験を通じて育まれましたか?
前職である富士通に勤めていた頃、3年目で突如リーダーとして抜擢されましたが 、これまでの立場と勝手が違いすぎて壁にぶつかり、悩んでいました。 そんな折に、上司が商談に同行してくれたことがありました。お客様先で上司が何気なく描いた図を見たとたんに、それまで沈黙していたお客様が堰を切ったように話し始めたのです。その瞬間、「図ってすごい」と衝撃を受け、図解の持つ力に強く惹かれたのが始まりです。 その後、図解について深く学ぶ中で、単なるツールとしての側面だけでなく、もっと根源的な、思想としての可能性を感じ始めました。そこで、社会人大学院生として、慶應義塾大学大学院SDM研究科へ入学し、アカデミックな側面から図解の持つ力を研究しました。そして、図解の可能性を追求し、社会実装するために、会社を立ち上げ「ダイアグラム思考」という思考法を創案するに至りました。
新着プロジェクト New Project

QWS チャレンジ
はじめてみませんか?
進めることができる内容であれば、分野や規模に制限はありません。
ぜひ、プロジェクトの更なる可能性を試してみませんか。
プロジェクトベースが
無料で利用可能!