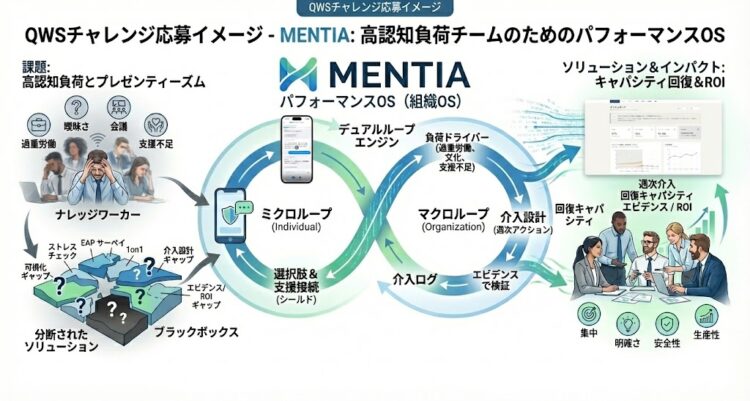見えないものに、どうやって寄り添う? 〜病室で孤独を感じる子どもたちへ〜
何にチャレンジするのか?
私たちは入院生活で生じる閉塞感や孤独感をやわらげることにチャレンジします。 閉塞感とは、病室という限られた空間に長期間とどまることで、学校や地域といった日常の場から切り離され、自由や選択肢を奪われてしまう状態を指します。多くの場合、子どもたちは窓の外に広がる当たり前の風景に触れられないこと自体が大きなストレスとなります。 孤独とは、面会制限や距離の問題によって家族や友人との交流が制限され、同世代との関わりが極端に少なくなることで生じます。多くの入院患者は同じ境遇を分かち合える仲間すら見つけにくく、治療以外の時間を誰とも共有できないことが心の負担となります。



なぜチャレンジするのか?
私は幼少期から繰り返した入院生活の中で、病室という限られた空間に閉じ込められ、友人や学校、外の世界との接点を失う強い閉塞感を味わいました。治療のつらさに加え、孤独や不安に押しつぶされそうになる経験は、自分にとって大きな原体験となりました。その体験から「同じ状況にある子どもたちに少しでも希望やつながりを届けたい」という思いが芽生え、チャレンジをしています。

どのようにチャレンジするのか?
私たちは、長期入院中の子どもたちに「外の世界とのつながり」を取り戻してもらうため、VRとアプリを組み合わせた体験型プラットフォームを開発しています。360度動画による「外の世界の疑似体験」と、アバターを通じた「患者同士の交流」、さらに病院が安全に利用を管理できる仕組みを備え、現場での実装を目指します。医療機関や企業との連携を進めながら、実証実験を通じて社会実装に挑みます。
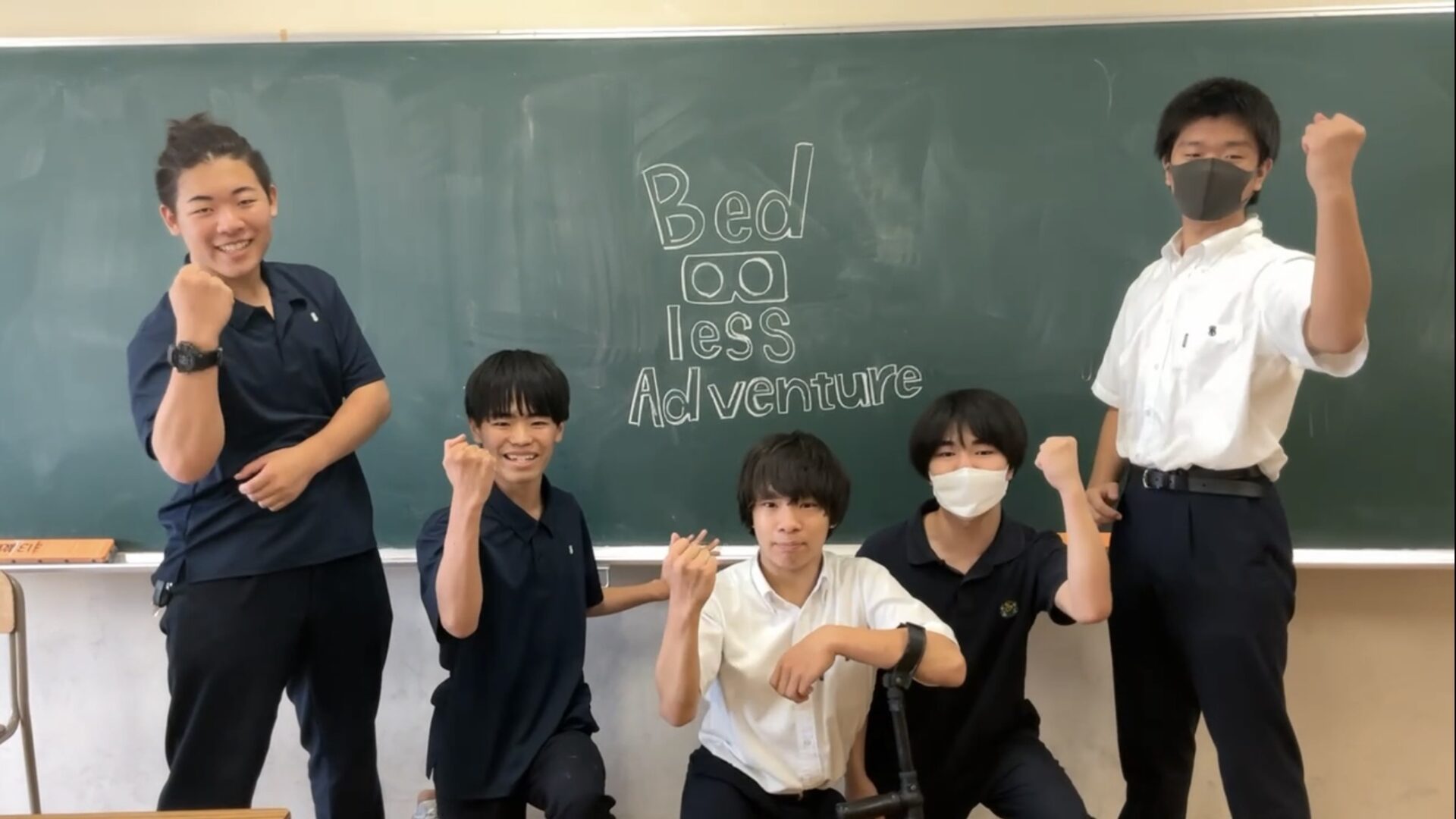

プロジェクトメンバー

寺田蒼立
寺田蒼立
聖学院高校レギュラークラス1年。 GICクラスの内部選抜に落ちたことから、自分の人生に立ち返り、自分の過去の体験を元にこのプロジェクトを立ち上げた。 現在、病院関連の施設でボランティアをしている。 同校の中高物理部の部長をしていた経験からマネジメントが得意。 また情報処理能力にも強みを持ち、JAPAN MENSAの会員資格も持つ。 ネパールやタイの研修など、海外研修にも参加している。

五井 泰地
五井 泰地
聖学院高校GICクラス1年。企業ゼミに所属している。 中三の頃、入院生活を経験し、このプロジェクトに参加。 中学校の頃はサッカー部に入部しており、体力面では自信あり。 ベースを弾くことや作曲が趣味。 数々のコンテストに応募し、人脈を広げることを目標に専念している。

沼尻 祥宕
沼尻 祥宕
聖学院高校GICクラス1年。 幼稚園生の頃より性やジェンダー、人間の感情の仕組みに関心を持ち、日々の実践と検証を通して理解を深めてきた。 中学2年生時には「日本語とエロス」をテーマに自由研究を実施。 現在はその研究を発展させ、人間の感情のメカニズムを論理的に言語化する探究を考えている。

佐藤 宇
佐藤 宇
聖学院高校GICクラス1年。 歩いていると他の人から目を逸らされることが最近の悩み。 美術部とボクシング部所属。 人のことの話をよく聞き、的確なアドバイスを出すことが得意。 チームの中でも盛り上げ担当。

原 拓海
原 拓海
聖学院高校レギュラークラス1年。 学業にも力を入れており、自分の知見を広めるためプロジェクトに参加した。 活動では、文章作成と情報収集を得意とする。 趣味は野球観戦、好きな球団はセリーグは横浜Denaベイスターズ、パリーグは千葉ロッテマリーンズである。
採択者コメント

リーダーインタビュー
あなたの[問い]は、どのような未知の価値に繋がると考えますか?
私の問い「見えないものに、どうやって寄り添う?」は、長期入院中の子どもが常に抱える閉塞感や孤独といった“目に見えない負担”に応答する新しい価値を生むと考えています。VRによって日常の風景を再体験したり、アバターを介して仲間や家族と交流することで、子どもは退屈さを軽減し、心理的安心感や自己選択による主体性を得られます。保護者にとっては、子どもの笑顔や成長を実感しながら交流の負担が軽減され、離れていても安心できる時間が生まれます。さらに病院関係者にとっては、患者のQOL向上を通じて医療スタッフの負担が減り、保護者からの信頼獲得や病院のイメージ向上にもつながります。身体的治療だけに偏らず、心のケアまで社会的に広げていく。この問いは、立場を超えた新しい価値観を提示すると考えています。
あなたの「問いの感性」は、どのような経験を通じて育まれましたか?
私の問いの感性は、「なぜ、入院中はこんなにも孤独なのか」という強い違和感から生まれました。私はこれまでに15回以上入退院を経験してきました。小児病棟では、病気の治療が最優先で、心のケアや社会とのつながりは後回しにされがちです。自由に歩くことも、外に出ることも、家族と自由に面会をすることも制限され、病室という閉ざされた空間に、ただ時間が流れていく感覚がありました。その中で感じたのは、「体は治っても、心が置き去りにされる」という現実です。入院中の子どもたちは、見えない孤独や閉塞感と毎日向き合っています。けれど、その感覚は病院の外には届きにくく、社会全体でもほとんど認識されていません。これは当事者と経験者しかわからない問題です。この経験から、「過去の自分と同じ境遇の子どもたちにどうアクションを起こすべきか」という問いが生まれ、その後「見えないものに、どうやって寄り添うべきか」と考え続けた結果、Bedless Adventureというプロジェクトにつながりました。私にとって、問いは理屈ではなく、実感から育まれてきたものです。この実感があるからこそ、今もプロジェクトに向き合い続ける原動力になっています。
QWSステージでの発表
新着プロジェクト New Project

QWS チャレンジ
はじめてみませんか?
進めることができる内容であれば、分野や規模に制限はありません。
ぜひ、プロジェクトの更なる可能性を試してみませんか。
プロジェクトベースが
無料で利用可能!