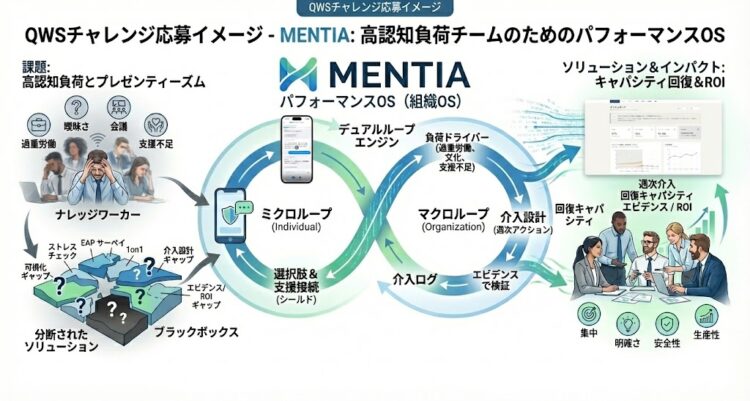手放されるモノの価値を最大化するには?
何にチャレンジするのか?
私たちTrash Lensは、「捨てるという行為を再定義し、資源の価値を最大化する社会システムの構築」にチャレンジします。現代社会では、不要になったモノが無造作に捨てられ、環境負荷の高い形で処理される一方、複雑化する分別ルールに生活者が対応することは困難になっています。また、リユースやアップサイクルといった資源活用の選択肢は存在するものの、それらを検討・比較する手段は限られており、多くの潜在的価値が失われています。
私たちのチャレンジは、AIとデジタル技術を活用して、この「捨てる」という日常的な行為に革命を起こすことです。具体的には、以下の3つの課題解決に挑戦します。
1. 複雑化する分別ルールの可視化と簡易化:地域ごとに異なる分別ルールをAIが自動判別し、誰でも簡単に正しい分別ができる仕組みを構築します。
2. 捨てられるモノの潜在的価値の発掘:AIが画像から特徴を検出し、リユースやアップサイクルの可能性を提示することで、捨てられるはずだったモノに新たな命を吹き込みます。
3. 資源循環のエコシステム構築:リユース・アップサイクル事業者、自治体、生活者をつなぐプラットフォームを創出し、資源が最適に循環する社会システムの実現を目指します。
このチャレンジを通じて、「捨てる」という概念そのものを変革し、誰もが意識することなく資源の最適な活用ができる社会の実現に貢献します。QWSという多様なプレイヤーが集まる場で、異なる視点や専門性を持つ人々と協働することで、より実効性の高いソリューションを生み出していきます。


なぜチャレンジするのか?
私たちがこのチャレンジに取り組む原点は、代表山本の幼少期からの連続した原体験にあります。お菓子の筒を灯台に見立て、緩衝材をビルにして小さな街を作る遊びを通じて、「捨てられるものにも価値がある」という気づきを得ました。中学時代には教室のゴミ箱を自主的に分別し、高校時代にはコンビニ弁当の容器の分別ルールの違いに疑問を持ち、「捨てたいモノを撮影するだけで自動で判別してくれる仕組み」の原型を開発しました。大学入学後には環境スタートアップ「ピリカ」でのインターン経験を通じて、環境問題に対するビジネスアプローチの可能性と社会的インパクトの重要性を実感しました。
このような個人的な原体験に加え、私たちが今このチャレンジに取り組む社会的背景として、以下の3つの課題が深刻化していることが挙げられます。
1. 環境負荷の増大と資源の枯渇:日本では年間約4,300万トンの一般廃棄物が排出され、その多くが焼却・埋立処分されています。世界的にも廃棄物の増加は深刻な問題であり、2050年までに廃棄物発生量は現在の70%増加すると予測されています。限りある資源を有効活用し、環境負荷を低減するための取り組みは、持続可能な社会の実現において喫緊の課題です。特に日本は資源の多くを輸入に頼っており、国内での資源循環の仕組みづくりは国家的な課題でもあります。
2. 分別の複雑化と生活者の行動変容の難しさ:環境意識の高まりにより分別の種類は増加傾向にありますが、地域ごとに異なるルールや特別な条件による分別方法の違いは、生活者にとって大きな負担となっています。既に多くの生活者が「ゴミの分別が面倒」と感じており、正しい分別行動を促すためには、より簡便で直感的な仕組みが必要です。また、環境配慮行動と個人の利便性のトレードオフを解消し、無理なく継続できる行動変容の仕組みづくりも課題となっています。
3. 資源としての価値の未活用とエコシステムの分断:捨てられるモノの中には、リユースやアップサイクルが可能なものが多く含まれていますが、その価値を見出し、適切な手段で活用するための仕組みが不足しています。リユース市場は年々拡大しているものの、まだ潜在的な可能性の一部しか活用できていません。また、生活者、リユース・アップサイクル事業者、自治体などのステークホルダー間の連携が不足しており、効率的な資源循環のエコシステムが構築されていないことも課題です。
私たちは、テクノロジーの力でこれらの課題を解決し、「捨てる」という行為を通じて資源の価値を最大化する社会を実現したいと考えています。QWSという場で多様なプレイヤーと協働することで、単なるアプリ開発にとどまらない、社会システムとしての変革を起こすことができると確信しています。
どのようにチャレンジするのか?
私たちは、「捨てる」という行為を再定義し、資源の価値を最大化する社会システムを目指しています。以下の3つの方法でこのチャレンジを進めます。
1. 使いたくなるアプリ開発で技術の壁をなくす
「これってどうやって捨てるの?」という疑問にスマホで撮影するだけで答えるアプリ『Trash Lens』を開発しています。このアプリの主な特徴は次の2つです。
・写真を撮るだけで5秒で解決 複雑な分別ルールを調べる必要はありません。カメラで撮影するだけで、お住まいの地域に合った正しい捨て方を瞬時に提示します。
・「捨てる」以外の選択肢も提案 「このモノは○○円で売れるかも」「こんなリメイク方法があります」といった、モノの新たな活用法も紹介します。
QWSでは、多様な人々と共にアプリの使いやすさをさらに向上させる機会を作ります。
2. 地域ぐるみの資源循環の輪を広げる モノの価値を最大化するためには、人や組織を繋ぐことが不可欠です。具体的には以下の取り組みを行います。
・渋谷区をモデル地区として資源循環を実践 QWSがある渋谷区をモデル地区に選び、地元のリサイクルショップやアップサイクル作家、自治体と連携した地域内の資源循環の仕組みを作ります。
・「欲しい人」と「手放したい人」をマッチング アプリ内でマッチング機能を開発し、手放す人と必要な人がチャットで気軽にやり取りできる仕組みを整えます。
・成功事例を見える化 「モノがどのように再生されたか」を共有し、資源循環の輪をさらに広げます。
QWSでは、異なる分野や専門性を持つ人々との交流を通じ、新しい連携や可能性を模索します。
3. 楽しみながら行動を変える仕掛けを作る
「環境に良いこと=面倒・難しい」というイメージを変え、楽しみながら自然に行動が変わる仕掛けを用意します。
・ゲーム感覚で継続できる工夫 資源循環への貢献度が可視化される・正しい分別でポイントが貯まるなど、続けたくなる仕組みを取り入れます。
・成功体験を共有するコミュニティ作り 「捨てるつもりだったモノが活用された」などの体験を気軽に共有できる場を作ります。
QWSでは、様々なイベントやワークショップを通じて「捨てるモノにも価値がある」という気づきを多くの人に広めます。

山本虎太郎

井上慎也
井上慎也
メガベンチャーやGAFMなどで環境マネジメントを担当し、Trash Lensに参画。代表の山本が株式会社ピリカでインターンとして従事していた際に、共に業務を行う。

小野源太
採択者からのコメント

しかし、現在の仕組みでシェアリングできる、有価物を中心とした不要品「未満」の不要品はまだまだ大量に家庭と企業の中に眠っていて、「ゴミ」として廃棄されてしまっていると思います。
しかし、「誰かにとってはゴミでも、誰かにとっては宝である。」そんな、適切な形で適切な人に届ければ価値となる「眠れる不要品」を呼び起こす可能性を秘めたTrashLensに、循環型社会の未来を感じ、応援します。
リーダーインタビュー
あなたの[問い]は、どのような未知の価値に繋がると考えますか?
私たちの「捨てるものにも価値がある」という問いは、以下のような未知の価値に繋がると考えています。
まず、「ゴミ」という概念の再定義です。現代社会では、使い終わったモノは「ゴミ」として扱われ、その価値は急速に失われます。しかし、私たちの問いは、不要なモノを単なる廃棄物ではなく、新たな価値創造の源泉として捉え直すことを促します。これにより、社会全体の資源に対する認識が変わり、廃棄物の発生そのものを減らす循環型社会の実現に近づくことができます。 次に、「無意識の環境貢献」という価値です。環境問題の解決には個人の意識や行動変容が不可欠ですが、多くの人にとって「環境のために行動を変える」ことは負担に感じられます。Trash Lensは、「捨て方を知りたい」という日常的な疑問に答えながら、自然と環境に良い選択ができる仕組みを提供します。特別な意識や手間をかけずとも、結果として環境貢献につながる社会システムの構築は、持続可能な社会への新たなアプローチとなります。 また、「コミュニティ型資源循環」という新たな価値も創出できると考えています。従来の資源循環は、自治体や企業が主導する大規模なシステムが中心でしたが、Trash Lensを通じて、地域や趣味などの小さなコミュニティを基盤とした、よりパーソナルな資源循環の仕組みを生み出すことができます。
さらに、「データ駆動型の資源最適化」という価値も創出できます。Trash Lensを通じて収集される「捨てられるモノ」のデータは、社会全体での資源配分の最適化に活用できる貴重な情報源となります。どのようなモノがいつ、どこで、どれくらい捨てられるのかを予測することで、リユース・リサイクル事業者の効率的な運営支援や、メーカーの製品設計改善など、サプライチェーン全体の最適化につながる可能性を秘めています。 これらの未知の価値は、単にゴミ問題を解決するだけでなく、人々の価値観や社会システムの根本的な変革につながる可能性を秘めています。今後の活動を通じて、これらの価値をより具体的かつ現実的なものとして社会に提示していきたいと考えています。
あなたの「問いの感性」は、どのような経験を通じて育まれましたか?
私の「問いの感性」は、幼い頃の何気ない遊びの中で芽生えました。小学生の頃、お菓子の筒を灯台に見立てたり、緩衝材をビルに見立てたりして、家の中に小さな街を作って遊んでいました。他の子どもたちがおもちゃで遊ぶ中、私は「捨てられるはずのもの」に新たな命を吹き込む喜びを見出していたのです。
この感性が社会課題への問いへと発展したのは、中学1年生の時にプラスチックのリサイクル工場を見学したことがきっかけでした。それまでは単にゴミとして埋め立てられると思っていたプラスチックが、実は分別され、洗浄され、再び原材料として活用されることを知りました。ゴミ箱の先でゴミを生かそうとしている人たちがいることに感銘を受け、教室のゴミ箱から一つずつ紙ごみを拾い上げて分別するようになりました。
しかし、クラスの友人から「世の中たくさんのゴミがあるのだから、君がこの教室のゴミだけ分別しても無駄だ」と言われたことで、個人の行動だけでなく、社会の仕組みから変えていく必要性を感じるようになりました。
高校3年生の時には、コンビニ弁当の容器の分別問題をきっかけに、地域によって異なる分別ルールの複雑さに気づきました。自分が正しいと思って行った分別が、学校では間違いとされた経験から、「捨てたいモノを撮影するだけで自動で判別してくれる仕組み」を作ろうと考え、Trash Lensの原型となるアプリを開発しました。
大学入学後、環境スタートアップの「ピリカ」でインターンした経験は、社会課題をビジネスで解決する可能性を実感する機会となりました。こうした経験の積み重ねが、「捨てるか、売るか」の二択ではなく、モノの価値を最大化する多様な選択肢を提供するという今の「問い」へと発展したのです。
QWSステージでの発表
新着プロジェクト New Project

QWS チャレンジ
はじめてみませんか?
進めることができる内容であれば、分野や規模に制限はありません。
ぜひ、プロジェクトの更なる可能性を試してみませんか。
プロジェクトベースが
無料で利用可能!