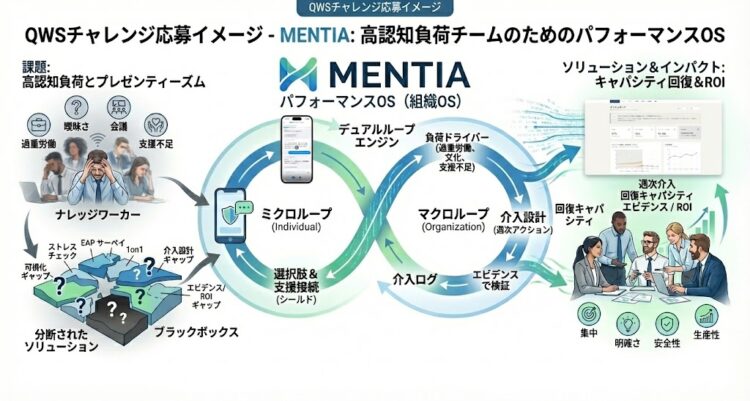「空の世界のチーム作り」×「災害対応」=「新しい災害対応」の姿が見えるかも?
何にチャレンジするのか?
私たちの問いは、『“災害対応”と“航空業界”という一見すると交わりがない双方の特性を紐解くと、「災害対応 × 空のチーム」という新しい災害対応の姿が見えるのでは?』というものです。
能登半島沖地震が発生した翌日の1月2日に羽田空港で発生した事故では、海上保安庁機に搭乗していた5名の海上保安官が命を落としました。 一方で、JAL機に搭乗していた379名の乗員・乗客の全員が救出されたことは、海外メディアから「奇跡」との賞賛を受けました。
公表された運輸安全委員会の『経過報告書』では、「非常脱出において重大な人的被害が発生しなかったことに関与した可能性がある事項」が記載されており、空のチームが大切にしている「チーム・リソース・マネジメント(TRM)」が深く関与していたことが見えてきます。
災害発生時には、「事前に準備したことだけ」では対応できないこともあり、その場その場で臨機応変な対応も必要になりますが、事前準備の考え方と現場での臨機応変な対応の進め方について、TRMの考え方を取り入れた「震災対応×空のチーム」という新しい災害対応の姿を、QWSでの対話を通じて形づくることを目指します。
私たちの思い描く新しい災害対応の姿とは、災害直後から地域内外の人々が助け合い、救助活動や復旧活動に迅速に対応し、人々が安心できる生活にすぐに戻ることができるようにすること。二次災害を最小限にし、人々の命と生活を守ること。そして世界のお手本となって、日本で育成された”減災エキスパート”人材が世界中で活躍し、どこで災害が起きても同じように人々の命と生活が守られることに貢献することです。
なぜチャレンジするのか?
1995年1月17日の早朝に、阪神淡路大震災が発生しました。プロジェクトリーダーである私自身も大阪の実家で被災し、日常が機能停止することを10代で経験しました。
祖母と母が被災した熊本地震では、被災で亡くなった方の4倍にもあたる方が関連死で亡くなられるなど、「震災を経ても“生き延びた”と安堵できない」ことを痛感しました。
そして、阪神淡路大震災から約30年が経過した2024年1月1日の夕方に、能登地方を震源とする最大震度7の地震が発生し、多くの尊い命が失われました。
社会は進化しているにも関わらず、ニュースに映し出された避難所の光景は、30年前の阪神淡路大震災の時と変わらないことに疑問を感じました。
多くの人が寒いであろう体育館に雑魚寝をし、幼い子供を抱えた人たちが避難所生活の難しさを話す映像を目の当たりにし、「被災者としての経験と航空業界での経験が役に立つのでは?」という問いが生まれました。
どのようにチャレンジするのか?
まず、私たちは活動の基盤となる一般社団法人を設立し、個々人ではなく法人として取り組みを進めていきます。
そして、能登半島沖地震が発生した翌日の1月2日に羽田空港で発生した事故に対して、公表された運輸安全委員会の『経過報告書』で述べられた空のチームが大切にしている「チーム・リソース・マネジメント(TRM)」が、様々な災害時にも多くの人の役に立てる仕組みを紐解いていきます。
災害発生時には、「事前に準備したことだけ」では対応できないこともあり、その場その場で臨機応変な対応も必要になりますが、事前準備の考え方と現場での臨機応変な対応の進め方について、TRMの考え方を取り入れた「災害対応×空のチーム」という新しい災害対応の姿を、QWSでの対話を通じて形づくることを目指します。
プロジェクトメンバー

藤岡 裕美子
藤岡 裕美子
新卒でCAとしてJALに入社後、国内線・国際線ともに乗務。その後、外資系ブランドや日本酒メーカーでのPR勤務を経て、サニーサイドアップに転職したことをきっかけに、渋谷区在住となり渋谷を愛する。能登震災の避難所が30年前と変わらぬ状況に違和感を覚え、本プロジェクトを構想。渋谷区で子育て奮闘中。

蔭山 幸司
蔭山 幸司
元航空管制官。25年のキャリアの中では、管制塔や管制センターなどの現場勤務、「空の道」の設計、訓練教官、霞が関での企画立案など様々な業務に携わり、人事院と協働で採用試験の変革も推進。
これらの経験から「人」という財の重要性を強く感じ、「人材教育」よりも「人財共育」との想いを強くする。
渋谷区在住、3児の父。渋谷区が進める「未来の学校」プロジェクトに興味津々。

橋本 知明
橋本 知明
渋谷区生まれ渋谷区育ち。新卒で三菱商事入社、中東、アジア、ロシアの天然ガス事業に携わり、長期研修でタンザニアに滞在。その後三菱商事を退職、英エクセター大学にて環境保全政策修士課程修了。小笠原海洋センターにて小笠原諸島の海洋生物の調査保全活動に従事。その後モザンビーク田舎町で農業とカフェを開業。2025年に日本に帰国し、(株)そらはなにて勤務。「豊かな暮らしとは?」について考える、1児の父。
採択者からのコメント

リーダーインタビュー
あなたの[問い]は、どのような未知の価値に繋がると考えますか?
When : 近い将来に起こり得る大きな自然災害が発生した時に、
Where : 日本の災害現場のみならず世界中の災害現場において、
Who : 教育訓練を受けたスペシャリストと一般市民の皆さんが「チーム」になって、
What : 『災害対応 × 空のチーム』という新しい災害対応を用いて、
Why : 人々が安全・安心に暮らしていけるより良い未来を創るために、
How : 子どもたちが学校で学ぶだけでなく、大学の教職課程で教員のタマゴも学ぶことで、
災害時に「事前に準備したこと」では対応できない場合に、
臨機応変な対応で自分や周りの命を守る可能性が高まることに繋がる
と、考えています。
そして、災害の直接被害から身を守り、避難所に移動した後は、より良い避難所運営のために必要なコア人財になることに繋がるとも考えています。
TRMは、国際法でも定められた世界共通の価値観なので、『災害対応 × 空のチーム』という新しい災害対応の姿は、日本だけでなく世界中に拡げていくことが可能なため、世界のあらゆる場所でお役に立てることに繋がると考えています。
あなたの「問いの感性」は、どのような経験を通じて育まれましたか?
1995年1月17日の早朝に、淡路島北東部を震源とする最大震度7の地震が発生しました。阪神淡路大震災です。
プロジェクトリーダーである私自身も大阪の実家で被災し、日常が機能停止することを10代で経験しました。その後も日本では自然災害が度々発生し、試練を乗り越えてきましたが、祖母と母が被災した熊本地震では、被災で亡くなった方の4倍にもあたる方が災害関連死で亡くなられるなど、「震災を経ても“生き延びた”と安堵できない」ことを痛感しました。
そして、2024年1月1日の夕方に、能登地方を震源とする最大震度7の地震が発生し、多くの尊い命が失われました。 阪神淡路大震災から30年が経過し、社会は進化しているにも関わらず、ニュースに映し出された避難所の光景は、30年前と変わらないことに疑問を感じました。多くの人が寒いであろう体育館に雑魚寝をし、幼い子供を抱えた人たちが避難所生活の難しさを話す映像を目の当たりにし、「被災者としての経験と航空業界での経験が役に立つのでは?」という問いが生まれました。
QWSステージでの発表
新着プロジェクト New Project

QWS チャレンジ
はじめてみませんか?
進めることができる内容であれば、分野や規模に制限はありません。
ぜひ、プロジェクトの更なる可能性を試してみませんか。
プロジェクトベースが
無料で利用可能!