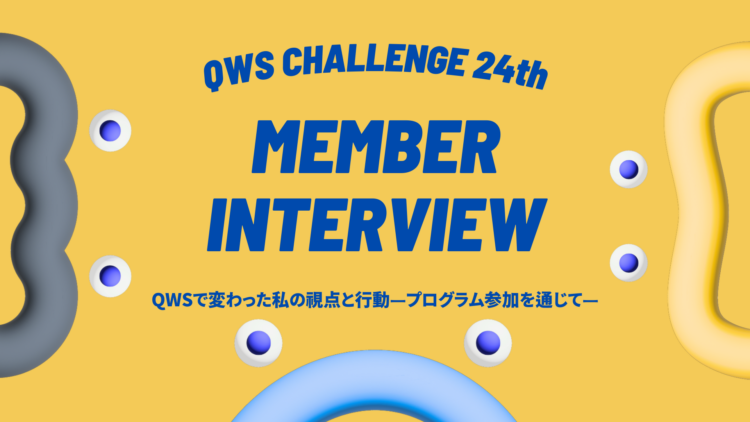病気の子どもと共にあゆむ あそびのブランド「POCO!」を運営する「Child Play Lab.」の猪村真由さん。QWSチャレンジ18期で採択以後、QWS内外のコミュニティや実証実験の機会を活用し、プロジェクトを進めてきました。
この記事は、2024年度中に活躍したQWSプロジェクトへのインタビューをまとめたSHIBUYA QWS Annual Report 2024に掲載された記事のロングバージョンです。プロジェクトのあゆみを振り返りながら、ブレイクスルーしたきっかけ、ターニングポイント等について伺っています。
1期目のフィールドにQWSを選んだのは「リスクを最大限に減らして、チャレンジできる環境だったから」
猪村真由さん(以下、猪村):学生起業で立ち上げた一般社団法人Child Play Labも、2025年3月でちょうど2期目に入りました。振り返ると、この一年は「POCO! アドベンチャーBOX」のプロダクト開発に注力した一年だったと思います。QWSチャレンジに採択された2024年2月は、看護学生を卒業する直前でした。当時の私は看護師国家試験を受けず、「起業家としてやっていくぞ」と腹を括っていたものの、事業の軸が定まり切っておらず、不安でした。
そんなタイミングで応募したのが、QWSチャレンジです。1期目の活動拠点としてQWSを選んだのには、明確な理由があります。それは、ここ(QWS)ならリスクを最大限に減らしつつ、思いっきりチャレンジできる場所だと思えたから。QWSには、過去にお世話になったコミュニティの関係者や大学の先輩、同期がメンバーとして活動していました。私にとって、これまでのつながりを活かしながら、安心してチャレンジできる土壌が整っていたんです。
QWSでの活動期間中は、3ヶ月ごとに目標を決めて、プロジェクトを進めてきました。最初の3ヶ月間で取り組んだのは、アドベンチャーBOXの開発です。まずはプロトタイプをつくり、仮説検証を繰り返しながら、子どもにとっての遊びとは?プロダクトをつくるとは?ということに必死に向き合いました。その甲斐あって、QWSステージ#18では優秀賞を受賞。延長採択を受けて、次の3ヶ月間ではプロダクトのブラッシュアップを目標に、実証実験のエリアを拡大させながら活動を進めました。この頃から、プロジェクトとして目標としていた病院内での展開もスタート。結果的に、半年間で70名ほどの子どもたちにアドベンチャーBOXを体験してもらうことができました。「楽しかった!」「こんなものが欲しかった」など現場からの反響も大きく、さらにはメディアに取り上げていただくこともしばしば。特に、GOOD DESIGN NEW HOPE AWARD 2024で最優秀賞を受賞できたことは、大きな自信になりました。

「それって子どもたちは見ているの?」メンターの言葉がきっかけで、組織縮小を決断
猪村:1期目の自分に点数をつけるなら、40点ぐらいかなと思います。自分が信じたことを貫いて、純度の高いプロダクトをつくることができたという点では良かったのですが、事業として形にしていく上では、自分の未熟さが目立ったからです。ものづくりを通して、目の前で何かが形になっていくことの喜びや、共感して人が集まってくることに甘んじていた自分がいたんですよね。だから自分たちのありたいbeingと事業としての判断を間違えてしまったところも今思うと、正直ありました。たらればですが、もっと結果にこだわってストイックにできたんじゃないかなと思うんです。
こうやって自己評価ができるのには、二つの言葉の存在があります。一つは子どもたちからの言葉。アドベンチャーBOXを使ってくれた子たちに、「次にどんなBOXが欲しい?」と聞いたら「一緒に話せる相手が欲しい」という言葉が返ってきたことです。どれだけBOXが良くても、子どもたちにとって大事なのは「誰と出会い、誰と過ごすか」。私たちが目指す社会の実現には、BOXだけを配るだけでは足りないことに気づかされた瞬間でした。だからこそ、最後に登壇したQWSステージ#20では、自分たちがBOX配り屋さんではないことを発表しました。
二つ目のきっかけは、メンターからの言葉です。メディアでの露出やアワードの受賞など、少しずつプロジェクトが広がっていくうちに、日頃からお世話になっているメンターに、「それって、子どもたちは見ているんだっけ?」と投げかけられたのです。プロジェクトを知ってもらうための広報活動は必要不可欠。ただ、それが目的になっていないかと問われた時、自分のポジションの取り方が少し間違っていたのかもしれないと気づかされました。もちろん広報活動に注力して、子どもたちを取り囲む現状を知ってもらうべくインフルエンサーとして活動していく選択肢もあったと思います。だけど私は看護師を辞めて、起業をしているーー。その原点に立ち返ると、もっと私自身が子どもたちと向き合い、泥臭く現場に潜り込んで活動していく必要性を痛感しました。知ってもらうだけではなく、目の前から着実に社会を変えていく使命がある、と再認識したんです。
そこから、社会にこの事業を根付かせていくために、本当に必要なことをメンバー間で話し合いました。悩みに悩んだ結果、一度、組織規模を縮小することを決定。パートナーで関わってもらっていたメンバーには本当に心苦しかったのですが、目の前の優先度と未来を天秤にかけた時、「これは今、乗り越えないといけない苦しみだ」と判断しました。それでも、この意思決定に不安や揺らぎがまったくないかと言われると、そうではないのが正直なところです。でも、だからこそ今は起業を決めた時と同じように、覚悟をもって事業に向き合えていると思います。現在は私含めフルタイム二人の体制に絞り、それぞれが現場に赴き、子どもたちと向き合いながら、言葉にならないインサイトをも取りにいくことに心血を注いでいます。今は毎日が闘いで、事業をつくっていくとはこういうことなのかなという緊張感を改めて感じているところです。

問いは変わらない。現場に徹し、あそびの哲学を追求し続ける
猪村:“How”は変わっているところもありますが、「心から湧き出てくる願いや目標が生きる力になりうるのか?」という問いは、ずっと変わりません。むしろ、問いへの思いは強まる一方です。2期目の目標は、ディープサクセスをつくること。声にならない声を拾い、事業として形(仕組み化)にしていくことです。現在は「アドベンチャーアシスト」という新しいサービスの開発に注力しています。「アドベンチャーアシスト」は、子どもたちのあそびを伴走するサポートプログラムのようなもの。私たちが子どもたちと実際に中長期にわたって「あそぶ」ことで、その子の個性が最大限に尊重される環境を一緒に作っていきます。伴走を通じて、その子が自分らしさを発揮できる経験を育むことを目指しています。この事業は1期目で子どもたちから得たフィードバックをもとにしていて、「何をするか」よりも「誰と、どう過ごすか」という関係性に重きを置いているのが特徴です。子どもたちと多くの時間を共にする親御さんからは「(自分の子どもの個性は理解しているので)うちの子、困っていないです」と言われることもあります。しかし、そういう親御さんにこそ、実はこのサービスが有効で、潜在的なニーズにアプローチしにいっていることを実感します。
よく「起業家は孤独」と言われることもありますが、そう感じる機会はこの一年、ほとんどなかったですね。なぜなら自分たちの孤独以上に、必死に歩みを進めている子どもたちが、目の前にいるから。私たちが向き合う子どもの中には、まだ治療法が見つかっていない病気とともに生きている子も多くいます。ご縁をいただいたお子さんの中には、この1年で、亡くなっていく子も見てきました。子どもたちが生を輝かせている限りは、自分たちも全力で向き合いたい。この仕事をしていると、近くで同じ時間を過ごすのは、今を全力で過ごし、命を輝かせきる人たちがほとんどです。こうして魂を燃やし続けられることは、尊いことなんだとつくづく感じます。
今、日本全国にはこどもの専門病院がおよそ30施設ほどあります。私たちがサービスを届けたい子どもたちは、ほとんどこの病院のどこかにいます。つまり、病院との関係性を築くことができれば、全国の子どもたちへ届けられる可能性が一気に広がります。だから、まずは全国の病院との関係づくりを5年以内にやり切りたいと思っています。
病院と学校の狭間で生きる子どもにとってのあそびとは何か。医学的に必要、社会的に必要とされている、ではなく、子どもの権利の観点においては守られるべきことであり、本質的に子どもが(あそびを)必要としているから必要なんだ、と証明できるように、既存のカテゴリには縛られない形の連携、ファンディングのあり方を丁寧につくっていきたいです。大きな話に聞こえるかもしれませんが、海外では病院内に私たちが取り組んでいるようなことを専門のスタッフが常駐する体制が整ってきており、決してできないことではないと思っています。
雇用が生まれ、範囲が広がっていくことで、他の教育現場にも影響を与えることができると思いますし、ひいては専門のスタッフでなくとも、子どもの存在を肯定し尊重した眼差しでの関わりしろは誰しも作ることができるはず。私たちの取り組みを通して、「あそびの哲学」を社会にインストールしていきたいですね。支援ではなく、真に社会に必要な存在になるために、問い続ける。そのために、まずは目の前の子どもたちと向き合い、声なき声に耳を傾け続けていきたいと思います。

猪村真由
猪村真由
QWSでの活動プロジェクト名:Child Play Lab.
一般社団法人Child Play Lab.は、「さぁ、ベッドの上から冒険を始めよう!」を合言葉に、病気の子どもたちが、自身の病気という経験を力に変えて、自分らしく生きていくことができる社会の実現」を目指し、病気の子どもとともにあゆむ あそびのブランド「POCO!」を運営しています。
この記事は「SHIBUYA QWS Annual Report 2024」に掲載されています。
2024年度活躍した他のプロジェクト情報も合わせてご覧ください。