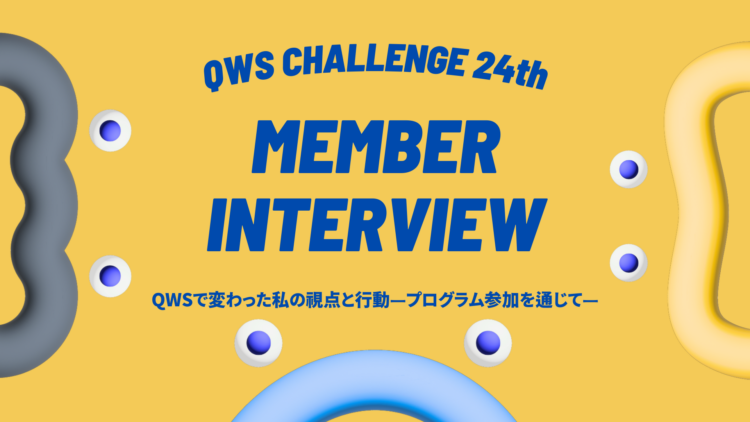「共創施設」を掲げるQWSには、様々なプレイヤーが「共創」を求めてやってきます。日々、大小問わず様々な共創が生まれていますが、今回はプロジェクトメンバー「Rendery」(株式会社SAMURAI ARCHITECTS)と、コーポレートメンバー「クウジット株式会社」の共創事例に密着。2社の出会いからQWSでの活動、そして最近立ち上げたジョイントベンチャーの事業内容に至るまで、詳しく聞いてみました。
この記事は、2024年度中に活躍したQWSプロジェクトへのインタビューをまとめたSHIBUYA QWS Annual Report 2024に掲載された記事のロングバージョンです。プロジェクトのあゆみを振り返りながら、ブレイクスルーしたきっかけ、ターニングポイント等について伺っています。
1期目のフィールドにQWSを選んだのは「リスクを最大限に減らして、チャレンジできる環境だったから」
クウジット株式会社 雙木(なみき)弘美さん(以下、雙木):加藤さんとの出会いは、QWSステージ#15(2023年7月開催)でした。そもそも、当時我々はまだQWSへ入会しておらず、弊社と共創・共走プロジェクトを進めている為末大さん(QWSコモンズ)のご紹介で、QWSを訪問。コワーキングスペース的な施設はいくつも見ていたものの、QWSはとりわけ素敵な場所だと思いました。すると、為末さんがキーノートトーク(QWSステージ冒頭にあるゲストによる基調講演)に登壇されるということで、応援に伺いました。その後のプロジェクトピッチも見ていこうと思った際のトップバッターがRenderyの加藤さんでした。
QWSでの活動期間中は、3ヶ月ごとに目標を決めて、プロジェクトを進めてきました。最初の3ヶ月間で取り組んだのは、アドベンチャーBOXの開発です。まずはプロトタイプをつくり、仮説検証を繰り返しながら、子どもにとっての遊びとは?プロダクトをつくるとは?ということに必死に向き合いました。その甲斐あって、QWSステージ#18では優秀賞を受賞。延長採択を受けて、次の3ヶ月間ではプロダクトのブラッシュアップを目標に、実証実験のエリアを拡大させながら活動を進めました。この頃から、プロジェクトとして目標としていた病院内での展開もスタート。結果的に、半年間で70名ほどの子どもたちにアドベンチャーBOXを体験してもらうことができました。「楽しかった!」「こんなものが欲しかった」など現場からの反響も大きく、さらにはメディアに取り上げていただくこともしばしば。特に、GOOD DESIGN NEW HOPE AWARD 2024で最優秀賞を受賞できたことは、大きな自信になりました。
Rendery 加藤 利基さん(以下、加藤):当時は会社を立ち上げたばかりで、生成AIを用いたリアルタイム建築パース作成で、設計者とクライアント間の意思疎通をスムーズにできる「Rendery」というサービスについて紹介していました。ピッチ時間は3分だったので、なかなか伝えきれなかったところもありましたが、興味を持っていただける方がいたらいいなと思ってお話ししました。QWSステージでは全プロジェクトのピッチ終了後、ネットワーキングの時間に雙木さんにお声がけいただきました。
雙木:お声がけさせていただいた理由は、サービスの内容はもちろん、「テクノロジーとデザインを活用して、すべての人々の空間をより豊かにすることを目指す」ビジョンにとても共感したからです。私自身、クリエイティブ出身ですがその後、経営を学び、取締役としてクウジットに参画しました。クウジットも「あるべき未来[空]を妄想し、現[実]とのギャップをテクノロジーで埋める」をミッションに掲げているので、加藤さんのピッチにとても心が動きました。
この日を機に「私たちもQWSに身を置くことで、加藤さんたちや他の企業、プロジェクトの皆さんとももっと一緒に何かできるのではないか」というQWSを訪問した時から感じていた期待が確信に変わり、その後、入会を決めることにしました。

「用がなくても顔を合わせられる場所がQWS」JV立ち上げの背景
加藤:その後、クウジット社もQWSに入会されて、お話しする機会が増えました。まずはQWSでイベントをやったり、プロジェクト単位でご一緒したりするなどして小さく始めて。そこから、2024年8月には、「ウェルビーイングな空間価値」モデル化事業での業務提携を発表させていただきました。当時の業務提携では、弊社が「ウェルビーイングな空間価値」モデル化サービスの提供、建築・都市デザイン領域の知見を基にした技術・ビジネス開発を、クウジット社が実空間におけるセンシング&データ分析、および笑顔づくりとウェルビーイング領域の知見を基にした技術・ビジネス開発を、という役割分担をして、取り組みました。同じAI領域といえど生成側に強い弊社と、データ解析に強いクウジット社ではできることが異なるんです。
雙木:まさに、“共創”ですよね。でもそれができたのは、日頃のコミュニケーションの積み重ねの賜物かなとも思います。QWSのいいところの一つに、用がなくても顔を合わせられることがあると思います。誰に話しかけてもいいというルールや「Question Break」といったちょっとしたイベントがあることで、全体に雑談できる空気が流れていますよね。
QWSにいることで日々顔を合わせることができる。それによって、状況を感じることができたのだと思います。「最近の加藤さん、なんか忙しそうだな」とか(笑)。こういった雑談の積み重ねから相互理解につながり、事業をスムーズに立ち上げられたのじゃないかと思っています。
加藤:こまめにコミュニケーションをとることができたのは、とても有難かったです。近況を報告させていただくこともあれば、こういうこともできるんじゃないか、などざっくばらんにお話しさせていただくこともよくありましたね。
その積み重ねもあって、おかげさまで、今年の6月にはいわば一つの集大成として、株式会社Maison Technologyをクウジット社と弊社のジョイントベンチャーという形で立ち上げました。Maison Technologyは、「世界のWellから空間のあり⽅を考える建築・都市に向けた、新たなテクノロジーデザインファーム」として、アルゴリズム開発やデータ解析、ウェルビーイングの実績があるクウジット社とAI開発やサービス設計に強みをもつ弊社の知見を集積させて、空間を起点とする様々なプロジェクトに取り組むことを目指しています。

雙木:この立ち上げに至ったのも、1年前の業務提携がきっかけです。当時、業務提携についてのプレスリリースを発表させていただいたのですが、市場からの反響が大きかったんです。まだ始まったばかりのタイミングだったのにもかかわらず、「どんなことができるのか?」といった、お問合せを多数いただきました。その時、「この共創によって、世の中に新しい価値を提供できるのではないか」という手応えみたいなものを感じられたんです。
キーワードは次世代継承、領域横断人材の育成。共創を通じて新たなチャレンジも
加藤:Maison Technologyはまだ始まったばかりですが、「やさしいテクノロジー」をモットーに、人々の空間・行動をより豊かにするプロジェクトを今後展開していく予定です。既に他社を交えた研究事業も始まっていますが、まだ言えないことも多く……。リリースをぜひ楽しみにしていただけると幸いです。
クウジット株式会社 末吉隆彦さん:この共創を通じて、プロジェクトはもちろんですが、クウジット社としては「次世代継承」にもチャレンジしていきたいと考えています。

雙木:奇しくも、加藤さんが起業した年齢は、私自身が独立した年齢とも同じなんです。加藤さんをはじめとする、若い世代とのコラボレーションから生まれるものをとても楽しみにしています。
また同時に、横断型人材の育成をしていく必要もあると思っています。私も加藤さんも専門領域はあれど他のメンバーがエンジニア、リサーチャーなどそれ以上にスペシャリスト。専門性も重要ですが、社会や他の領域との接点を作り、共創やイノベーションを生み出していくには、我々のような領域横断型の人材も、これからの時代に必要になってくると思っています。なかなか成果が見えづらいポジションではありますが、そういったところも取り組んでいきたいですね。
加藤:弊社は私以外は基本的にエンジニア集団。事業領域、会社設立時の年齢、組織内でのポジションなど雙木さんとは共通点が多いんですよね(笑)。色々学ばせていただきながら、共に新しい価値や問いを社会に提示していきたいと思います。

株式会社SAMURAI ARCHITECTS 加藤利基(写真左)
QWSでの活動プロジェクト名:Rendery
クウジット株式会社 雙木弘美(写真中央)、末吉隆彦(写真右)
Renderyとクウジットは、世界のWellから空間のあり⽅を考える建築・都市に向けた、新たなテクノロジーデザインファームとして、2025年6月にジョイントベンチャー株式会社Maison Technologyを設立。
この記事は「SHIBUYA QWS Annual Report 2024」に掲載されています。
2024年度活躍した他のプロジェクト情報も合わせてご覧ください。