AI時代において、芸術はいかに社会課題の解放に貢献できるか?
何にチャレンジするのか?
芸術体験が人々にもたらす変容と、その社会的価値を定量的に示すこと。芸術と科学の新しい交わりを探求する。

なぜチャレンジするのか?
芸術の価値は主観的で見えにくく、社会的意義が正当に評価されていないため。

どのようにチャレンジするのか?
双方向型芸術体験プログラムを実施し、参加者の心理尺度、行動変容などを測定。データをもとに、芸術の社会的価値を可視化し、今後の芸術と科学の新しい協働モデルを探る。
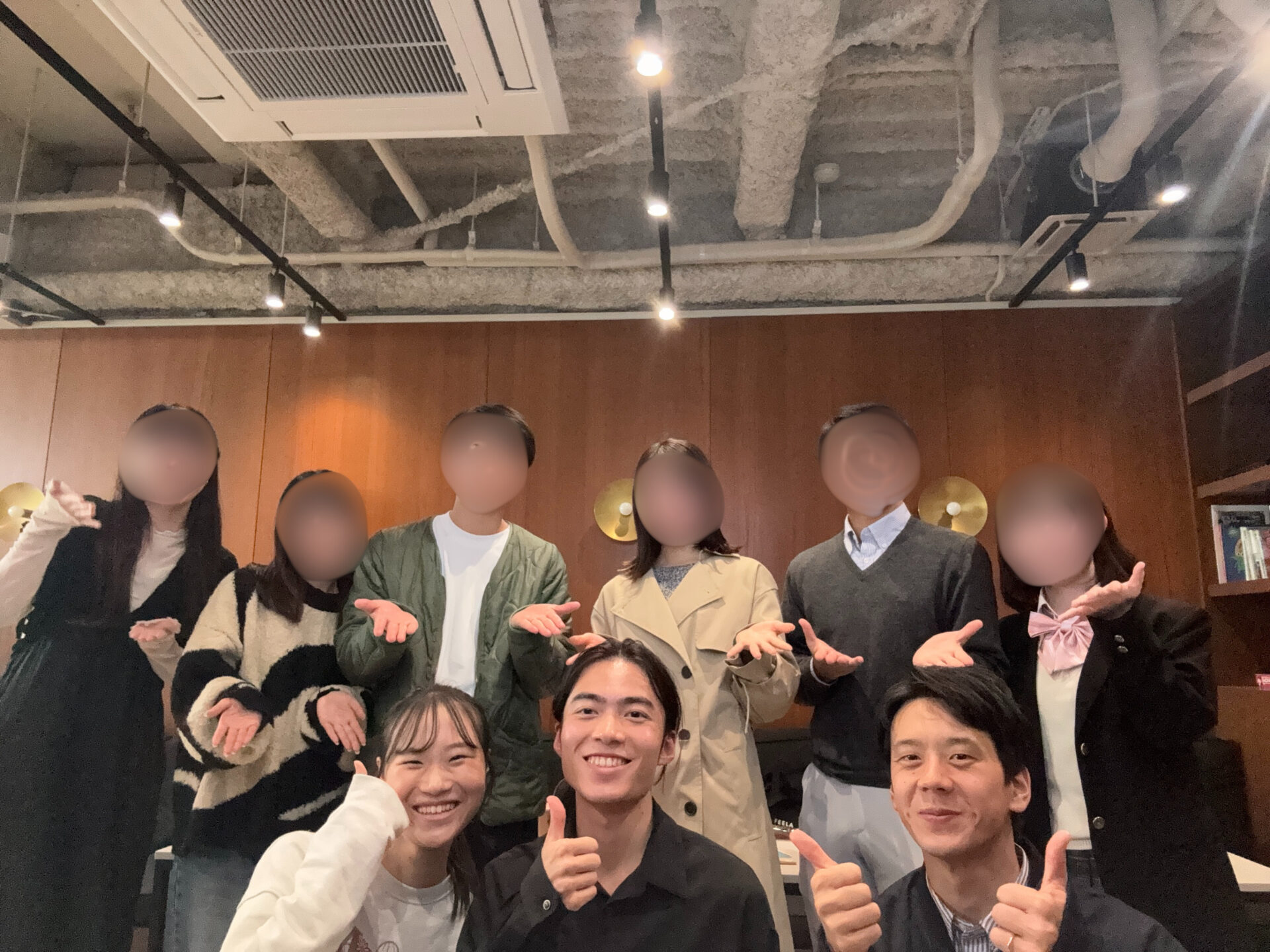
プロジェクトメンバー

黄 松毅

上杉 未宇

大塚 康平
大塚 康平
東京/本業×岡山/副業に取り組むクロスボーダーサラリーマン。 大手金融会社のシンクタンクにて社会課題解決に向けたコンサルティング業務を経験。現在は大手通信会社でデータやAIを活用した新規事業開発、顧客のDX推進、スタートアップ協業に従事。 また地元岡山県の自治体と連携し、まちづくりや地元産業支援・新規事業創出に取り組む。1児の父。 九州大学大学院工学府修了。
採択者コメント

リーダーインタビュー
あなたの[問い]は、どのような未知の価値に繋がると考えますか?
私の問い「AI技術が進化する現代において、芸術はどのように人々の心に影響を与え、社会課題の解放に貢献できるのか?」は、まだ誰も明確に実現していない新しい価値に繋がると考えています。具体的には、「芸術による心身のケア」が、社会全体の幸福度や生産性向上に直結するという価値です。この価値は、現在の科学的アプローチでは十分に解明されていない部分が多いですが、私は芸術を通じてこれを実証したいと考えています。
あなたの「問いの感性」は、どのような経験を通じて育まれましたか?
私の「問いの感性」は、AI研究と芸術活動という二つの異なる領域を行き来する中で自然に育まれてきました。AIが急速に進化する現代、私はその技術がいかに人々の生活を変えるかを日々感じながら、同時に芸術に深く関わっていました。AIの精緻な計算能力や効率化の能力には驚くべきものがありますが、その一方で、AIが決して再現できない「人間らしさ」に強く引かれるようになりました。 私が芸術活動に本格的に取り組み始めたのも、この感覚が根底にあったからです。AIの進歩によって、効率や最適化が求められる現代社会において、ますます「人間らしさ」や「感情」の重要性が増していることを痛感しました。機械は決して持つことのできない、人間の複雑で繊細な感情や、創造性の自由さ、それを表現するための芸術には、無限の可能性が広がっていると感じています。 私の問いの中で重要なのは、「AIにはできない、芸術が人々の心にどう影響を与えるのか?」ということです。AIがどれだけ進化しても、心を揺さぶり、共感を生み出す力、そして社会の中で価値を持つ「人間らしさ」を生み出す芸術の力は、無限に重要であり、これからの時代においてますます輝きを放つべきだと確信しています。
新着プロジェクト New Project

QWS チャレンジ
はじめてみませんか?
進めることができる内容であれば、分野や規模に制限はありません。
ぜひ、プロジェクトの更なる可能性を試してみませんか。
プロジェクトベースが
無料で利用可能!






