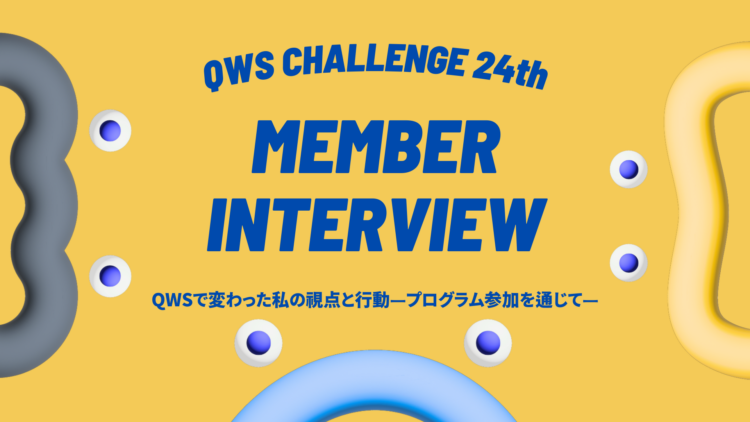QWS STARTUP AWARDをきっかけに出会い、共創へとつながったスタートアップと大企業。
今回は、数分で心が夢中になるショートドラマレーベル株式会社HA-LU代表取締役 岡氏と、同社へ賞を贈った東急株式会社 峰﨑氏に、応募から受賞、そして二日で8,000人を動員した「渋谷アオハル祭2.0祭」に至るまでの軌跡を伺いました。
執筆:冨田阿里
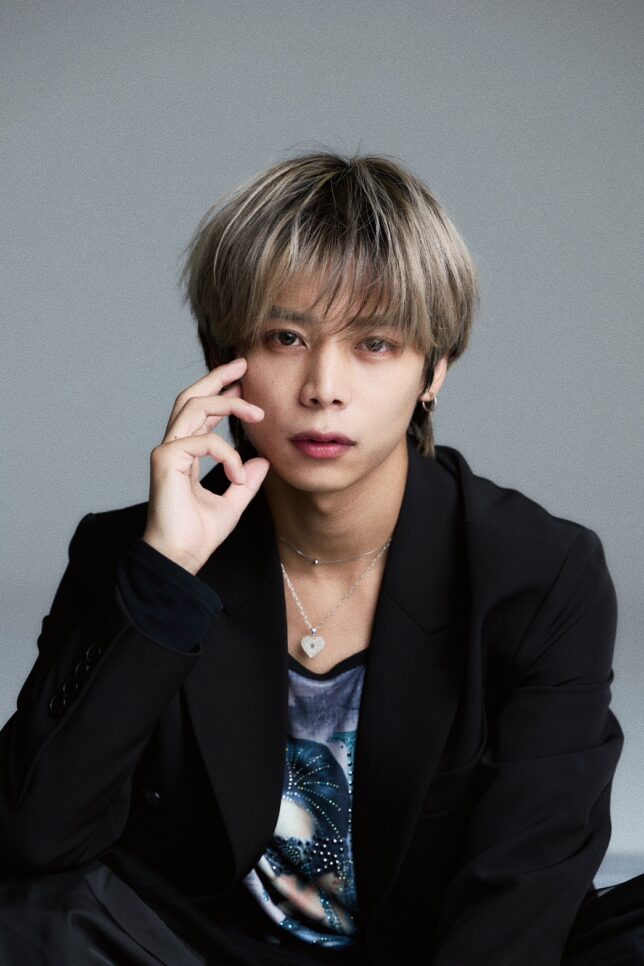
岡春翔さん
岡春翔さん
2000年生まれ、自身のSNSの総フォロワー50万人を超えている。ハル学園の制作・プロデュースを行い、ショートドラマレーベル「HA-LU」を設立。設立1年で、運用SNSアカウントは総再生3億再生を超え、総フォロワー数37万人超え。鈴木おさむ氏、yutoriの片石氏、サイバーエージェント・キャピタル、ブーストキャピタル、スタートアップファクトリーから資金調達する。今年4月にカンブリア宮殿20周年の年に最年少起業家で出演する。さらにForbes 30 under 30 Asia 2025にも選出

峰崎大輔さん
峰崎大輔さん
2008年に東急株式会社に中途入社。入社後、PASMO電子マネー事業、駅ナカWi-Fi事業、交通・屋外広告担当などの領域を担当。2019年に社内起業の制度を活用してふるさと納税事業を立ち上げした後に、2024年4月より現部署に配属。渋谷エリアの開発戦略の策定や行政・他事業者との関係づくり、対外PRなどを行っており、渋谷におけるスタートアップとの共創企画も担当している。
応募のきっかけと、二社の出会い
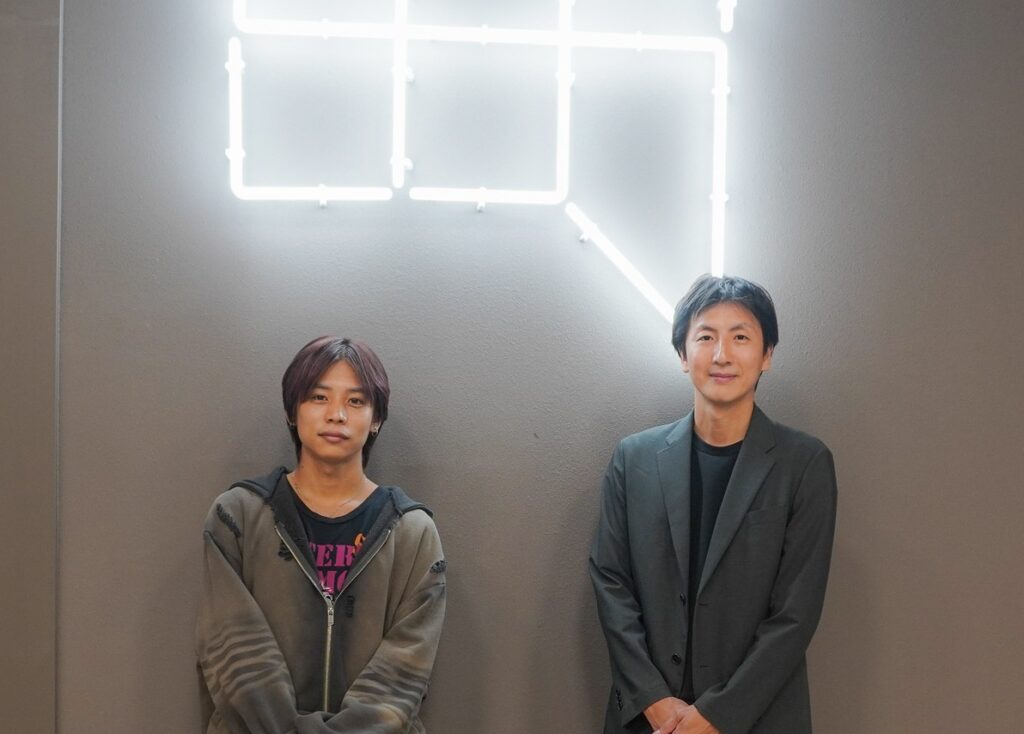
――岡さん、まずはQWS STARTUP AWARDに応募した経緯を教えてください。
岡さん:応募のきっかけは知人からの紹介でした。実はそれまでピッチイベントに出たことがなく、有名なピッチイベントにも応募したことがありませんでした。以前から、“渋谷でやりたい”という気持ちはずっとあって、QWS STARTUP AWARDであれば、その思いを形にできるかもしれないと思い、応募しました。
――渋谷のスタートアップピッチと言えば、QWS STARTUP AWARDしかないですね!
峰﨑さんはなぜ、HA-LUへ東急賞をお贈りされたのでしょうか?
峰﨑さん:どのスタートアップも非常に素晴らしかったのですが、東急としては、受賞者を選ぶ際に大きく二つの基準を設けていました。ひとつはコンシューマ向けのアイデア・サービスであること。もうひとつは、すでにある程度形になっているサービスであることです。副賞として渋谷のスクランブル交差点のビジョンに広告を出すことを考えると、アイデア段階ではなく、サービスがすでに提供されていれば、実際に渋谷の街の中で多くの人々の目に触れることで、インパクトを生み出すことにつながります。その点、HA-LUさんはどちらにも当てはまります。そして、サービス内容も、その対象・ターゲットも、渋谷らしい。岡さんの存在感も含めて、ピッチを聞いていて、未来を感じさせるものでした。
共創に至るまで
ーーー東急賞を受賞後、副賞内容を超え共創までつながっていきましたがどのような流れだったのでしょうか?大企業とスタートアップの協業で苦戦したお話しを伺うことも多いですが、ご苦労はありましたか?
岡さん:受賞後、峰﨑さんが次々と東急社内の方を紹介してくださいました。広告やイベント、まだお話し出来ない別プロジェクトまで、いまも並行して動いているものがあります。当時は会社を立ち上げて半年で、大企業との連携の進め方も広告のマナーも分からないことだらけで、峰﨑さんにご迷惑をおかけしてしまったかもと思っています。「稟議」という言葉すら知らなかったくらい(笑)。そんな僕たちにも、真摯に向き合ってくださり、とてもありがたかったです。
峰﨑さん:特に大きな苦労というのは感じませんでした。むしろ私たちが、Z世代の視点や熱量に学ばせてもらうことが多かったです。以前から社内でも、「若者のトレンドをもっと理解しなければ」という声はありましたが、なかなか自分たちだけではつかめない。このプロジェクトを推進する上で社内で理解してもらえるかなー…と不安でしたが、「(今のZ世代文化というものを)分かってないという事実が再認識できた、任せるよ」と言ってもらえて、進めることが出来ました。だからこそ熱意のあるHA-LUさんと組んだ意味は大きかったと思います。

具体的な取り組み内容は、渋谷の文化祭
ーーー受賞から、5ヶ月で取り組みが表に出たと伺いました。

岡さん:はい!取り組みの象徴が『渋谷アオハル祭2.0祭』です。僕自身が男子校出身で青春を象徴する文化祭に憧れがあったことから、渋谷で誰もが参加できる文化祭をつくろう!と考えました。俳優やインフルエンサー、アーティストが集まり、キッチンカーを出して、渋谷の真ん中で若者たちが盛り上がるお祭りを開催しました。
僕のロマンだったのが、スクランブル交差点のQFRONTの大型ビジョンに広告を出すこと。学生時代、初めて渋谷に来て見上げた景色が忘れられなくて。当時はこんなところに自分が広告を出せるなんて考えもしませんでしたが、“ここに出せたら最高だな”と思っていた場所に、自分のプロジェクトを映すことができました。いま、思い出しても感慨深い経験で、そのときの映像は今もLINEのホーム画面にしています。またそれだけではなく、峰﨑さんが副賞の範囲を超えて支援してくださいました。

峰﨑さん:東急は媒体として、渋谷のQ’S EYE(QFRONTビルのビジョン)を始めとしたサイネージのみのご提供予定だったのですが、駅構内のポスター、あとは電車の中吊りでも告知をお手伝いさせていただきました。岡さんたちも、中吊り用の特別な形式に合わせてデザインを用意してくださったりと、協力的に動いていただきました。本当にすごい盛り上がりでしたね。
ーーーお二人の話を聞いていて、大成功だったことが伝わります。
岡さん:僕たちは、これまでデジタルの世界で生きてきましたが、初めてリアルな場で大人と若者が一緒に共創できた。それが最大の学びでした。設立1年未満の会社と、歴史ある企業が、日本一の場所、渋谷で挑戦できるんだという実感は、夢をさらに大きくしてくれました。
成果としては、2日間で8,000人を集めることができました。デジタルとリアルが共存し、目に見える形でコンテンツを届けられたのは初めての経験でした。
峰﨑さん:私自身も、もとはIT企業出身で、東急には転職で入社をしました。社内にデジタル関連企画を持ち込もうと挑戦をしていましたが、なかなか難しい部分もありました。しかし、外部のデジタルに強い人と社内のアセットを組み合わせると、大きく動かすことが出来る、という肌感覚はありました。今回も外部、それもデジタルを活用した若者文化のプロフェッショナルといえる岡さんたちとの取り組みなので、上手くいく感覚は持っていました。特に今回は、協業先企業の社歴に関係なく挑戦できることを証明できたのは大きな成果です。
受賞がもたらした気づき
ーーーこの取り組みが、どのように社会へ影響を与えると思いますか?
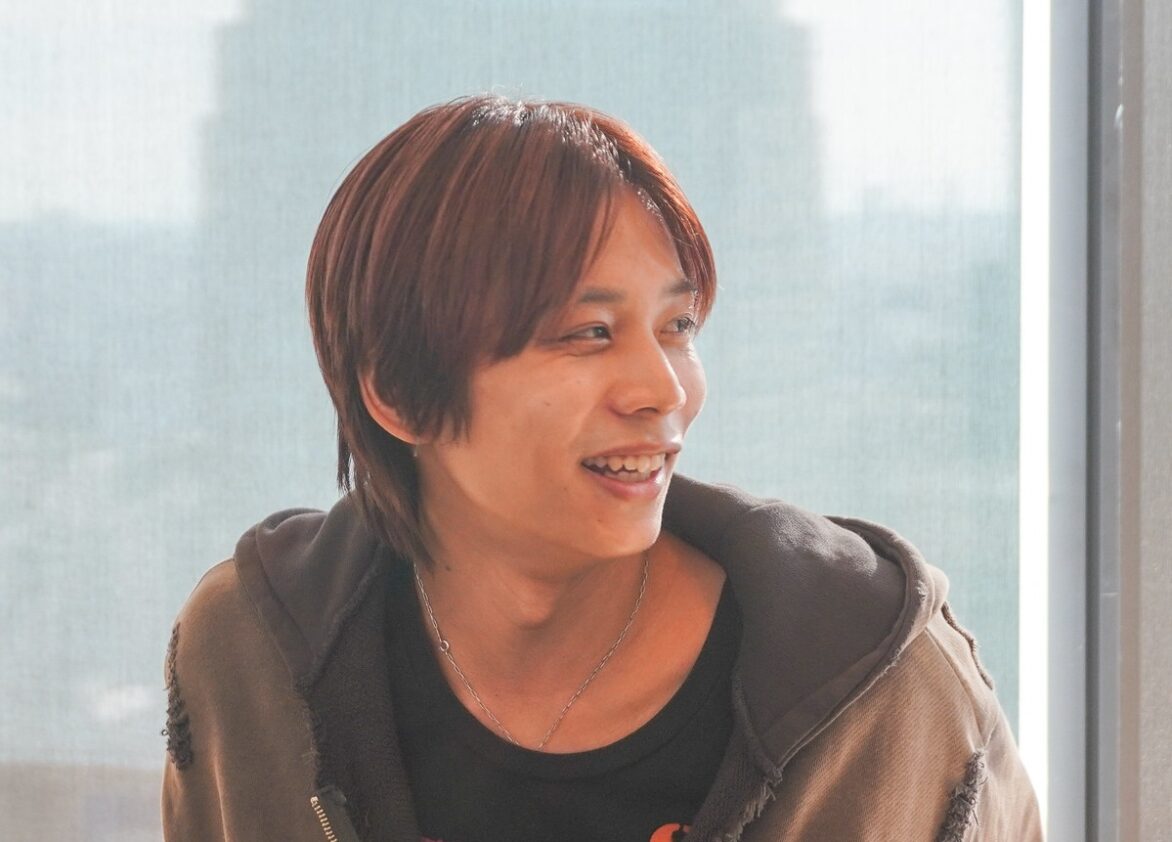
岡さん:この質問で気づいたのですが、僕はこれまで自分のために行動をしてきました。青春できなかった自分のために会社も立ち上げた。でも、今は違います。近年、SNSの功罪で自己肯定感が低い人が増えています。これまでは教室の友達と比べればよかったのに、今は世界中のセレブの生活がスマホで見られるので、自分が頑張るよりも、誰かを推した方が楽だよね。という風潮もあり、推し活が当たり前になってきています。
僕はこの一年で、自分の青春を体現することができました。これからは渋谷発で、若者たちが頑張れば自分の理想の未来をつくれると信じられる文化をつくりたいです。そして、「セイシュン(青春)」という言葉を世界に流行らせたいです。
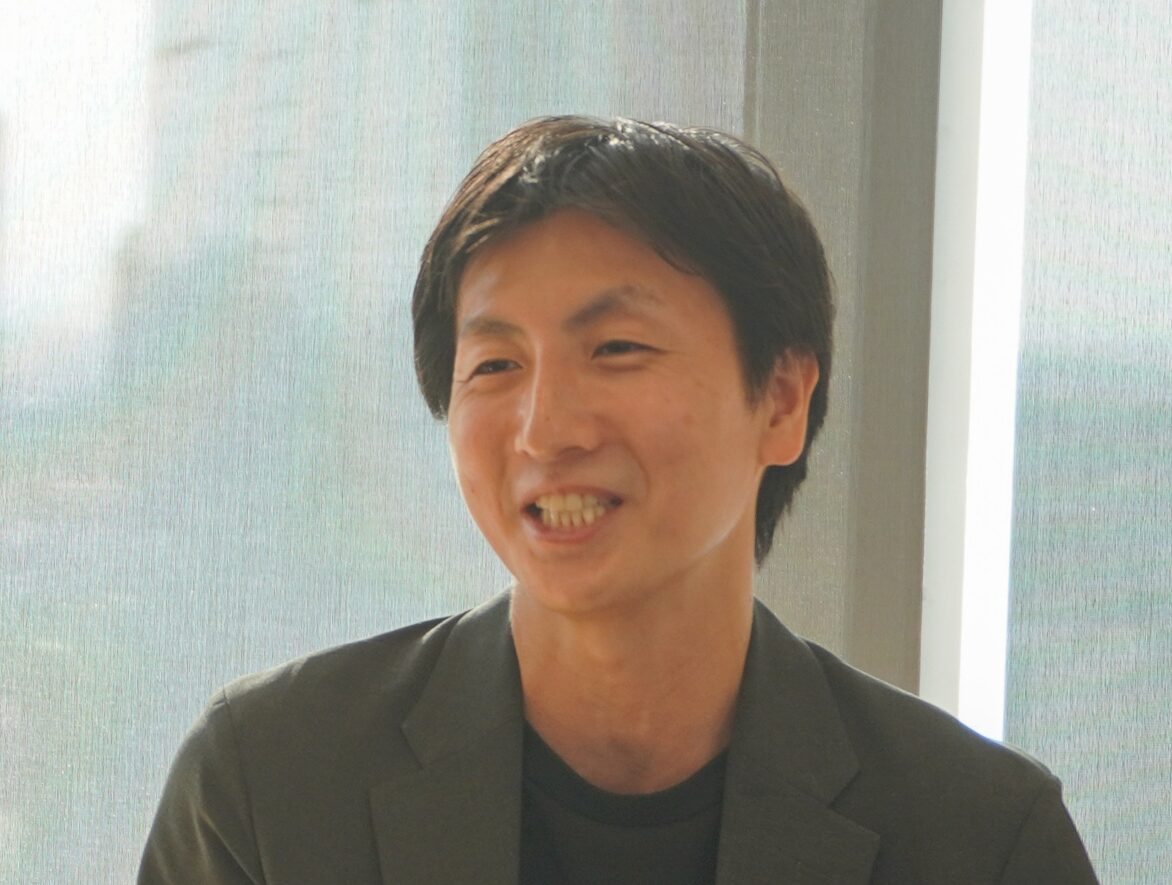
峰﨑さん:岡さんは経営者であると同時に、文化を担う創業者としての存在感があります。Forbes 30 Under 30 Asia 2025にも選ばれていますし、スタートアップ経営者にとどまらず、文化人としての活躍も期待しています。
またHA-LU社には、是非渋谷発として、今後全国、そして世界で、「SEISHUN(青春)」というワカモノの熱狂が生まれる手助けをしてほしいですね。
岡さん:はい、渋谷だけでなく、地方の街や地域にも、世界中へSEISHUN文化を広げていきたいです。青春は、いくつになっても誰もが楽しめるもの。その可能性を世界で実現していきたいと思います。
ーーー最後に、QWS STARTUP AWARDへの応募を検討しているスタートアップへメッセージをお願いします。
峰﨑さん:QWS STARTUP AWARDは、単に賞を贈る場ではなく、共創のきっかけをつくる場です。賞をお贈りする相手だけではなく、贈らせていただかなかったスタートアップとも、現在進行形で協業を検討しています。
「こういう企業と出会えたらいいな」という明確なイメージがあるわけではないですし、熱意を持った方にお会いしたいです、なんて自分が言うまでもなく、起業されている方は皆さんが熱意に溢れていらっしゃるでしょうし。 ただ一つお伝えするとしたら、ピッチの技術ではなく、本質的なところをストレートにぶつけてほしい!と思っています。
岡さん:そうですね。僕たちは設立半年強の会社で、とても光栄な賞をいただいて、ピッチイベントは、非合理なことがあるんだな!って思いました。
だって、Gジャンに金髪の僕がピッチをしたのです。もし合理的なAIが審査員だったら、そんなリスクのありそうな先を選べないんじゃないかって。 QWSって場では、そんな非合理的なことが起きるんです。
ーーー非合理的なこと!これからもそんなことが起きつづけるアワードにしていきたいです。岡さん、峰﨑さん、貴重なお話しをありがとうございました! 設立間もないスタートアップと歴史ある大企業が協働し、街や若者文化に新たな価値を生み出したこのプロジェクトは、単なる受賞だけでなく、共創の可能性を示す事例としても意義があります。
現在、QWS STARTUP AWARD 2026へのエントリーを募集しています。詳しくはこちらをご覧ください。