「AIとミツバチは、共に未来をつくれるのか?」 ― テクノロジーと自然の共生から考えるソーシャル・イノベーション ―(QWSアカデミア 早稲田大学)

イベント概要
- 日付
- 2025/11/28(金)
- 時間
- 13:30 - 16:30
- 場所
- CROSS PARK (SHIBUYA QWS内)
- 参加費
- 無料
- 定員
- 50名程度
【SHIBUYA QWSオリジナルプログラム ”QWS ACADEMIA” 】
大学と連携した「未知の問い」と出会うプログラムです。大学には多様な「問い」と向き合う学生や研究者がいます。「QWS ACADEMIA」は、単に知識が伝達される授業ではなく、双方向に刺激を与え合い、化学反応を生み出すことを目指します。
■開催趣旨
AIと社会システム、そして人との関係を再構築する挑戦として、「AI×養蜂×ソーシャル・イノベーション」をテーマに議論する国際セッションを開催します。
第一部では、米国スタートアップBuzzHiveの創業者Michael “Mike” Bronikowski氏を迎え、AIを活用したスマート巣箱の開発や都市養蜂の未来を紹介します。日本からは「銀座ミツバチプロジェクト」副代表の田中淳夫氏が登壇し、都市と自然をつなぐ日本型養蜂の知見を共有します。何れの講演も日英の逐次通訳が入ります。
第二部では、参加者が英語と日本語のグループに分かれ、「AIと生物多様性」「ランドスケープとビジネス」など多様なテーマでワークショップを展開し、テクノロジーと自然の共生を探ります。
興味のある方は、是非、ご参加ください!
■日時:11月28日(金)13:30-16:30
■対象:大学生・大学院生/一般
■定員:50名程度
■参加費:無料
■会場:渋谷スクランブルスクエア15階 SHIBUYA QWS クロスパーク
■主催:SHIBUYA QWS Innovation協議会
■共催:早稲田大学グローバル科学知融合研究所/神奈川県立保健福祉大学イノベーション政策研究センター/Beyond 2020 NEXT PROJECT
■協賛:NPO法人銀座ミツバチプロジェクト/一般社団法人ミツバチプロジェクト・ジャパン
/Bass Center for Leadership Studies and Binghamton Center of Complex Systems (CoCo), Binghamton University, State University of New York
■後援:日本ソーシャル・イノベーション学会
■プログラム
13:10 開場
13:25 QWS紹介
司会 朝日 透(早稲田大学理工学術院 教授/グローバル科学知融合研究所 所長)
13:30 開会挨拶及びニューヨーク州立大学ビンガムトン校 Joey Tsai准教授紹介
島岡 未来子(早稲田大学戦略センター 教授/
神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科 教授)
第一部 *逐次通訳あり
13:35 招待講演 「AI巣箱とBuzzHiveのビジョン」
Mike Bronikowski(BuzzHive 共同創業者・CEO)
14:10 特別講演 「都市養蜂とコミュニティの力」
田中 淳夫(NPO法人銀座ミツバチプロジェクト 副代表)
14:45 休憩
第二部
司会 松本 綾香(早稲田大学 一貫制博士課程先進理工学専攻2年/Beyond 2020NEXT PROJECT 幹事長)
14:50 アイスブレイク
15:00 グループワーク1
15:30 グループワーク2
16:00 グループプレゼンテーション(各2分)
16:25 閉会挨拶
服部 篤子(大和大学政治経済学部政治・政策学科 教授)
■登壇者プロフィール
Mike Bronikowski(BuzzHive 共同創業者・CEO)

BuzzHive(https://buzzhivetech.com/)の共同創業者でありCEO。BuzzHiveはAI搭載のスマート巣箱を開発し、ミツバチの健康状態を監視・解析することで受粉や蜂蜜生産の最適化を目指すスタートアップ企業。Bronikowski氏の使命は「ミツバチの言語を解読すること」。ソーラーパワーで稼働するセンサーを導入し、温度・湿度・重さに加え、ミツバチの羽音を機械学習とAIで解析し、蜂群に異変が起きた際に養蜂家へアラートを送る仕組みを構築している。その技術は、気候変動や害虫など多くの課題に直面するミツバチの保護にもつながる、社会的価値の高いアプローチである。ニューヨーク州立大学ビンガムトン校Watson School of Computingの修士課程在籍中であり、AIを専攻している。
田中 淳夫(NPO法人銀座ミツバチプロジェクト 副代表)

「銀座ではちみつが採れたらおもしろいよね」との想いから、2006年銀座ミツバチプロジェクトを立ち上げ、銀座の街の活性化とミツバチが住める街づくりを提唱し、屋上緑化を推進する。また、地方との交流で、顔の見える関係の構築に尽力。都市養蜂のパイオニアとして各地のミツバチプロジェクトの発足に協力し、全国各地にミツバチ仲間を広げている(https://gin-pachi.jp/#about_us)。
■実行委員
島岡 未来子(早稲田大学 研究戦略センター 教授/神奈川県立保健福祉大学 ヘルスイノベーション研究科 教授)

早稲田大学第一文学部卒業後、国際NGOで管理職を経験後、(公財)地球環境戦略研究機関(IGES)特任研究員。早稲田大学商学学術院WBS研究センター助手、研究戦略センター准教授を経て現職。2013年早稲田大学公共経営研究科にて博士(公共経営)取得。文部科学省「グローバルアントレプレナー育成促進事業(EDGEプログラム)」、「次世代アントレプレナー育成事業(EDGE-NEXT」の採択を受け、WASEDA-EDGE 人材育成プログラムの運営に携わる。2019年度春学期早稲田大学ティーチングアワード総長賞受賞。起業家教育では、デザイン思考、リーンスタートアップなど複数科目を担当。文部科学省アントレプレナーシップ推進大使。
服部 篤子(大和大学政治経済学部政治・政策学科 教授)

奈良市出身。大阪大学大学院国際公共政策研究科修了。阪神・淡路大震災を機に、NPO研究の普及を目指す総合研究大学院大学のスコーププロジェクトに参画。その後、2009年一般社団法人DSIAを設立し、「ソーシャル・イノベーション」の推進と人財育成事業に取り組む。同志社大学政策学部教授などを経て、2025年より現職。日本ソーシャル・イノベーション学会理事。専門はソーシャル・イノベーション、社会起業論,公共経営論、公共政策。
2019年より同志社ミツバチラボと称して同志社烏丸キャンパスにて実際に養蜂を伴う科目を行い、現在は宇治、志賀にて活動を移動、継続している。
Chou-Yu (Joey) Tsai (Osterhout Associate Professor of Entrepreneurship, School of Management, Binghamton University / State University of New York)

Joey Tsai is the Osterhout Associate Professor of Entrepreneurship at the School of Management, Binghamton University. He earned his B.S. and M.S. in Psychology from National Taiwan University and his Ph.D. in Leadership and Organizational Behavior from Binghamton University. Before returning to Binghamton, he served on the faculty at California State University and Penn State University. Joey’s research explores entrepreneurship and leadership, with a particular focus on how leaders and teams drive innovation and venture success. His work has appeared in leading publications, including Journal of Applied Psychology, Harvard Business Review, and Journal of Organizational Behavior. He is a recipient of the SUNY Chancellor’s Award for Excellence in Teaching. Currently, he serves as the Associate Director of the Bass Center for Leadership Studies and as a fellow at the Center for Collective Dynamics of Complex Systems. In addition, Joey serves on the editorial review board for The Leadership Quarterly and mentors student entrepreneurship teams competing in the New York State Business Plan Competition and the FuzeHub Commercialization Competition.
朝日 透(早稲田大学理工学術院 教授/先進理工学部長・研究科長/グローバル科学知融合研究所 所長)

1986年早稲田大学理工学部応用物理学科卒業、1992年博士(理学)、2007年経営学修士。2013年先端科学・健康医療融合研究機構 機構長、2016年ナノ・ライフ創新研究機構 副機構長、2019年早稲田大学総合研究機構 グローバル科学知融合研究所所長、2021年W-SPRINGインターンシップ・キャリア支援責任者兼ライフイノベーション審査委員長を務め、学際的研究を推進し、イノベーション人材の育成に取り組む。2024年より、早稲田大学理工学術院先進理工学部長・研究科長。専門はキラル科学、生物物性科学、結晶光学、機能性薄膜、循環型食料生産システムの研究。
鬼頭 朋見(早稲田大学 理工学術院創造理工学研究科 教授)

東京大学工学部卒業、同大学院工学系修士課程、博士課程修了。博士(工学)。複雑な経済社会におけるさまざまな価値創造の実現と持続について、領域融合的なアプローチで取り組んでいる。近年は特に、スタートアップや新興技術のポテンシャル発掘、チームワークによるアイデア創出など、イノベーションエコシステムの未来を見据えた研究プロジェクトを多数推進している。
松本 綾香(早稲田大学先進理工学研究科一貫制博士課程先進理工学専攻 2年/Beyond 2020 NEXT PROJECT幹事長)

早稲田大学生物物性科学研究室 (朝日研究室) に所属。専門は物理化学、キラル科学、結晶光学。現在、早稲田大学本庄高等学院で非常勤講師を務める。アントレプレナーシップの養成をミッションに掲げる学生団体Beyond 2020 NEXT PROJECTに2020年度から参加し、2022年度に総務、2023年度からは事務局長を務めたのち、2025年度より幹事長を務める。国連を支える世界こども未来会議PJ、SDGs教育カリキュラムPJ、アントレプレナーシップ教育PJメンバー。
村田 光陽(東京農工大学BASE博士後期課程3年/K-1タスクフォースメンバー)

東京農工大学BASE鈴木研究室で昆虫学を専攻。食用コオロギ用の餌開発やコオロギの系統解析などを進める。昆虫食にも関心を持ち、様々な昆虫料理を実践。コオロギの竜田揚げを開発し、学園祭で販売。カンボジアでコオロギ用給水装置を開発。内閣府ムーンショット型研究開発事業 目標5「地球規模の食料問題の解決と人類の宇宙進出に向けた昆虫が支える循環型食料生産システムの開発」プロジェクトの学生社会実装グループ『K-1タスクフォース』メンバー。
藍原 朋弘(早稲田大学先進理工学研究科 一貫制博士課程先進理工学専攻1年/K-1タスクフォース代表)
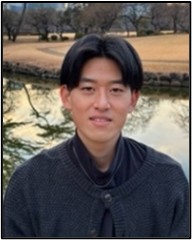
早稲田大学生物物性科学研究室生物応用班昆虫ユニットに所属。現在、深層学習を用いた動画解析によるコオロギの共食い行動の解明を目指して研究に取り組んでいる。内閣府ムーンショット型研究開発事業 目標5「地球規模の食料問題の解決と人類の宇宙進出に向けた昆虫が支える循環型食料生産システムの開発」プロジェクトの学生社会実装グループ『K-1タスクフォース』代表。
内木 望睦(東京農工大学応用生命科学科 4年)

東京農工大学 応用生命科学科大学院生物システム応用科学府 食料エネルギーシステム科学専攻研究室に所属。現在、動画解析及び時計遺伝子の解析によるミヤコカブリダニの概日リズムの確立、及びより優れた生物農薬への応用を目指し研究に取り組んでいる。内閣府ムーンショット型研究開発事業 目標5「地球規模の食料問題の解決と人類の宇宙進出に向けた昆虫が支える循環型食料生産システムの開発」プロジェクトの学生社会実装グループ『K-1タスクフォース』」に参加。
細田 凜々子(早稲田大学人間科学部4年)

早稲田大学人間科学部人間環境科学科に所属。専攻は文化人類学・都市人類学。ミツバチとその生態環境を人類学的視点から研究しており、都市養蜂から転地養蜂まで、全国の養蜂家を訪ねている。早稲田大学ボランティアセンターWAVOC内の「ラオス学校建設教育支援プロジェクト」では幹事を務め、教育格差の是正を掲げるNPO法人BORDER FREEの立ち上げにも初期メンバーとして参画。現在は、「早稲田大学での養蜂活動の実現」を目指し、学内外のネットワークづくりや企画立案に取り組んでいる。
伊能 龍之介(東京海洋大学海洋工学部4年)

東京海洋大学海洋工学部流通情報工学科・橋本研究室に所属。専門は物流、研究分野は数理最適化。『パレットローディングにおける積み付け個数の最大化』を主題に、2Dストリップパッキングに基づく整数計画を検討し、荷物のサイズから T-11 型パレットでの概算最大積載数を即時に読み取れる「選定表」を整備している。学内外の研究会での発表や共同検討を通じ、モデルの強化と改良の継続的アップデートを進め、「使える最適化」としての実装と普及を目指している。
吉浪正敬(東京海洋大学海洋工学部 4年)

東京海洋大学海洋工学部流通情報工学科に所属。強化学習を用いたマルチエージェントシミュレーションの研究に取り組んでいる。
物流や交通の分野において、複数の自律型エージェントが協調的に行動する環境をPython上で構築し、特に自動車同士の協調行動に焦点を当てて研究を進めている。また、Unityを活用した三次元シミュレーション環境の構築にも取り組み、AIの意思決定モデルによって制御されるエージェントをゲームエンジン上で動作させることを目指している。学外ではプログラミングサークル「NePP」に所属し、ゲーム開発やWebアプリケーション開発にも積極的に携わっている。
木下皓太(東京農工大学工学部4年/K-1タスクフォースメンバー)
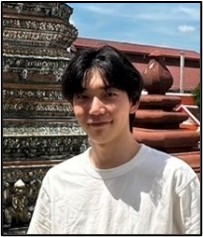
東京農工大学工学府生命工学専攻研究室に所属。現在、D-アミノ酸投与によるフタホシコオロギの成長への影響を解析し、D-アミノ酸が昆虫の発育や代謝に及ぼす生理的役割の解明を目指して研究に取り組んでいる。内閣府ムーンショット型研究開発事業 目標5「地球規模の食料問題の解決と人類の宇宙進出に向けた昆虫が支える循環型食料生産システムの開発」プロジェクトの学生社会実装グループ『K-1タスクフォース』」に参加。
長濵良門(東京農工大学工学部4年/K-1タスクフォースメンバー)

東京農工大学工学府生命工学専攻研究室に所属。現在、気温や光周期に関わらず強制的に休眠状態に入る「内因性休眠」という環境適応の分子メカニズムを解明することを目的に、エンマコオロギ属を対象としたマルチオミクス解析を進めている。内閣府ムーンショット型研究開発事業 目標5「地球規模の食料問題の解決と人類の宇宙進出に向けた昆虫が支える循環型食料生産システムの開発」プロジェクトの学生社会実装グループ『K-1タスクフォース』」に参加。
太田菜緒(東京農工大学工学部4年/K-1タスクフォースメンバー)

東京農工大学工学府生命工学専攻研究室に所属。現在、コオロギ上科における水平伝播遺伝子の模索とその進化的意義の考察及びアリヅカコオロギのゲノム構築に取り組んでいる。内閣府ムーンショット型研究開発事業 目標5「地球規模の食料問題の解決と人類の宇宙進出に向けた昆虫が支える循環型食料生産システムの開発」プロジェクトの学生社会実装グループ『K-1タスクフォース』」に参加。
梅原沙和香(東京農工大学工学部4年/K-1タスクフォースメンバー)

東京農工大学工学府生命工学専攻研究室に所属。現在、真核微細藻類である珪藻の、休眠メカニズムおよびその多様性の解析に取り組んでいる。内閣府ムーンショット型研究開発事業 目標5「地球規模の食料問題の解決と人類の宇宙進出に向けた昆虫が支える循環型食料生産システムの開発」プロジェクトの学生社会実装グループ『K-1タスクフォース』」に参加。
熊澤有紗(お茶の水女子大学人間文化創成科学研究修士1年)

ライフサイエンス専攻食品栄養科学コース・栄養教育学研究室に所属。
現在は、「昆虫食に対する消費者心理」をテーマに研究を進めている。具体的には、昆虫食はなぜ人々に受け入れられにくいのか、どのような情報発信が受容性を高めるのか、といった点に焦点を当てている。過去には、コオロギハンバーグの嗜好性向上に関する研究にも携わっており、昆虫食が将来的に食の1つの選択肢となるには何が必要かを、日々考察している。管理栄養士・栄養士の資格を有しており、学会等では健康的な食生活や食教育について議論を行っている。
圷恵麻(早稲田大学国際教養学部4年)

早稲田大学国際教養学部4年。Sustainability Studiesを専攻し、経済学ゼミでゲーム理論を用いたメカニズムデザインを学ぶ。現在は、より持続可能な食糧循環を実現するための市場戦略や流通システムの構築をテーマに研究を進めている。
学外では、食料廃棄物を水アブによって循環させるマレーシアのスタートアップで現地インターンを経験。現在はその取り組みを日本に広めるために活動しており、Tokyo Startup Gateway 2025 セミファイナリストに採択された。
杉本晃一(東京農工大学 生物生産科学専攻 博士1年)

東京農工大学連合農学研究科博士課程に在籍し、仲井まどか研究室に所属。専門は昆虫病理学で、ウイルス―宿主相互作用を中心に、ウイルスを用いた生物的防除がいかに害虫抑制を成功させるかの機構解明に取り組む。サイカブトとOrNVの感受性差や感染に伴う行動変化を、RNA-seq・画像行動解析・数理モデルで多層的に解析し、実装可能な防除戦略の基盤構築を目指す。東京理科大学理学部数学科を卒業しており、純粋数学の素養を活かし、茶樹害虫チャノコカクモンハマキにおける昆虫ウイルス抵抗性遺伝子の複素解析による新しい同定方法の開発という研究も展開している。
【ABOUT SHIBUYA QWS】
2019年11月1日、渋谷駅直結・直上に開業した渋谷スクランブルスクエア。SHIBUYA QWS(以下QWS)は、その15階に位置する会員制の施設です。「問うだけじゃなく、出会うだけじゃなく、生み出すだけじゃなく、世界を変えよう。」をコンセプトに掲げ、多様なバックグラウンドを持つプレイヤー達の[問い]を交差させることで、未知の価値に繋がるムーブメントを生み出すことを目指しています。
https://shibuya-qws.com/
【ご回答をいただいた個人情報を含む内容について】
いただいた個人情報は渋谷スクランブルスクエア(株)の個人情報管理規定に基づき、管理し、また、使用後は適切な方法で廃棄処分いたします。https://shibuya-qws.com/privacy-policy
【当イベントの記載情報について】
登壇者やプログラムに関する情報については、変更や追加決定事項があり次第、随時更新をさせていただきます。





