GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 2025特別シンポジウム「ベンチャービジネスの醍醐味は何だろう?:What is Real Pleasure of Venture Business?」

イベント概要
- 日付
- 2025/11/15(土)
- 時間
- 16:50 - 21:10
- 場所
- スクランブルホール (SHIBUYA QWS内)
- 参加費
- 無料
- 定員
- 180名程度 ※対象者ごとに人数制限がございますのでご注意ください
【SHIBUYA QWSオリジナルプログラム ”QWS ACADEMIA” 】
大学と連携した「未知の問い」と出会うプログラムです。大学には多様な「問い」と向き合う学生や研究者がいます。「QWS ACADEMIA」は、単に知識が伝達される授業ではなく、双方向に刺激を与え合い、化学反応を生み出すことを目指します。
【イベント概要】
Global Entrepreneurship Network(GEN/)が毎年11月に世界180カ国以上で同時期に開催するGLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 2025(GEW 2025)を2025年11月17日(月)〜11月23日(日)に開催します。GEW2025は起業家精神を育むためのグローバルなフェスであり、「起業を身近なものに、誰もが挑戦できるものに」というメッセージを掲げ、世界中の政府機関、企業、大学、スタートアップ支援団体が連携して、さまざまなイベントを実施しています。
日時:2025年11月15日(土)16:50-21:10
会場:渋谷スクランブルスクエア15階 SHIBUYA QWS(スクランブルホール)
対象:高校生、高専生、大学生、大学院生、大学教職員、研究員、社会人 他
定員:180名程度
参加申込先:https://qws-academia1115.peatix.com/
主催:SHIBUYA QWS Innovation 協議会
共催:早稲田大学理工学術院、早稲田大学グローバル科学知融合研究所、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科、上智大学、Global Entrepreneurship Network、文部科学省 宇宙航空科学技術推進委託費「ECLSS環境における人間の快適性を支える製品・サービスデザイン人材育成プログラム」、サスティナブルな未来食の普及に向けた産官学共創コンソーシアム、Beyond 2020 NEXT PROJECT
後援:ベンチャー稲門会
この度、GEW2025の一大イベントとして、2025年11月15日(土)17:00-21:00、渋谷QWS スクランブルホールにおいて、「ベンチャービジネスの醍醐味は何だろ?:What is Real Pleasure of Venture Business?」と題した特別シンポジムを早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学が連携して合同共催で開催します。
宇宙・AI・量子・ナノテク・メタバースの分野で注目のスタートアップのキイパーソンらが登壇し、これまでの道のりや今後の展開など熱い思いを語ります。さらに、パネルディスカションでは会場の皆さんとインタラクティブに議論します。
万障お繰り合わせの上、ご参加くださいますよう、お願い申し上げます。
司会 野中 朋美(早稲田大学 創造理工学部 教授)
16:50-17:00 開会挨拶
西口 尚宏(Global Entrepreneurship Network 日本代表/上智大学 特任教授)
【宇宙】
17:00-17:30 基調講演
白坂 成功(株式会社シンスペクティブ 共同創業者/慶應義塾大学大学院
システムデザイン・マネジメント研究科 委員長)
17:30-17:50 講演
畠山 祥(Number ホールディングス 代表/総合研究大学院大学 博士2年)
17:50‐18:10 講演
田中 克明(株式会社amulapo 代表取締役CEO)
【AI】
18:10-18:30 講演
松山 洋一(株式会社エキュメノポリス 代表取締役CEO)
18:30-18:50 講演
丸山 祐丞(EAGLYS株式会社 CSO)
18:50-19:00 休憩
司会 松本 綾香(早稲田大学 一貫制博士課程 先進理工学専攻2年)
【量子】
19:00-19:20 講演
武笠 陽介(株式会社Quanmatic代表取締役CTO)
【ナノテク】
19:20-19:40 講演
平野 梨伊(グラフェナリー株式会社 代表取締役社長)
【メタバース】
19:40-20:00 講演
田中 大貴(株式会社Urth CEO/早稲田大学 建築学専攻 博士3年)
20:00-20:30 パネルディスカション1
パネリスト 白坂 成功/畠山 祥/田中 克明/松山 洋一 モデレーター 朝日 透
20:30-21:00 パネルディスカション2
パネリスト 丸山 祐丞/武笠 陽介/平野 梨伊/田中 大貴 モデレーター 朝日 透
21:00-21:10 閉会挨拶
朝日 透(早稲田大学 先進理工学部長・研究科長)
ご参考
*Global Entrepreneurship Network: https://www.genglobal.org/
*Global Entrepreneurship Week: https://www.genglobal.org/gew/events
【登壇者】
西口 尚宏(Global Entrepreneurship Network 日本代表/上智大学 特任教授)

シリアルアントレプレナー。Global Entrepreneurship Network とStartup Genome の日本代表。 内閣府 ムーンショットアンバサダー 。既存企業へのイノベーション経営の浸透とスタートアップ・エコシステムづくりの両面から日本社会の活性化に取り組んでいる。スウェーデン国立研究所(RISE)認定のイノベーションマネジメント・プロフェッショナル。ISO TC279 イノベーション・マネジメント委員会 日本国内審議委員会の委員長を7年務めたのち、現在はAmerican Network for Innovation(ANI)の理事と共に米国国内審議委員会委員。文部科学省のEDGE及びEDGE-NEXTの構想段階から深く関与し、有識者会議委員を足掛け10年継続。経済産業省 産業構造審議会グリーンイノベーションプロジェクト部会委員、その他の政府委員会や研究会委員を歴任。世界銀行グループのオフィサー、マーサー社ワールドワイドパートナー、産業革新機構執行役員などを経て現職。上智大学経済学部経営学科卒、ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院卒。
白坂 成功(株式会社シンスペクティブ 共同創業者/慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 委員長)

東京大学大学院修士課程修了(航空宇宙工学)、慶應義塾大学後期博士課程修了(システムエンジニアリング学)。大学院修士課程修了後、三菱電機株式会社にて15年間、宇宙開発に従事。「こうのとり」などの開発に参画。大学では、大規模システム開発、技術・社会融合システムのイノベーション創出方法論などの研究に取り組む。2004年より慶應義塾大学にてシステムデザインの教鞭をとり、2010 年より同大学院システムデザイン・マネジメント研究科准教授、2017年より同教授。2023年10月よりSDM研究科委員長。内閣府革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)のプログラムマネージャーとしてオンデマンド型小型合成開口レーダ(SAR)衛星を開発。その技術成果を社会実装するために株式会社Synspectiveを創業(日本スタートアップ大賞2022文部科学大臣賞受書)。内閣府宇宙政策委員会、内閣官房デジタル市場競争会議、経産省 産業構造審議会 グリーンイノベーションプロジェクト部会等、多くの委員として政府の活動を支援。
畠山 祥(Number ホールディングス 代表/総合研究大学院大学 博士2年)

富山県高岡市出身の起業家・博士研究者。総合研究大学院大学に在籍。早稲田大学在学中に4つのテクノロジー企業を創業し、AI技術を活用した動画編集自動化ソフトウェア「Ready」の開発や、動物のリラックス音楽を提供する「One by One Music」など、多岐にわたるプロジェクトを手掛けている。現在はJAXA宇宙科学研究所にて、宇宙版Googleマップの開発や小惑星からの地球防衛に関する研究に従事しながら、5社を経営している。NHK「阿佐ヶ谷アパートメント“天才数珠繋ぎ”」などメディアにも出演。
松山 洋一(株式会社エキュメノポリス 代表取締役/早稲田大学 GCS研究機構 知覚情報システム研究所 客員准教授)
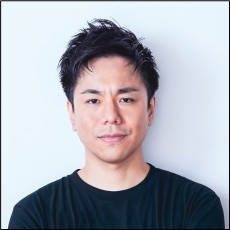
早稲田大学大学院 基幹理工学研究科にて博士(工学)を取得後、米国カーネギーメロン大学に博士研究員として会話エージェントの研究開発と産学連携プロジェクトを推進。2019年より早稲田大学 GCS研究機構 知覚情報システム研究所 准教授。JST START、JST A-STEP、NEDO 人と共に進化する次世代AI開発事業、NEDO STS、NICT Beyond 5G 革新的情報通信技術事業、デジタル庁実証事業など複数の競争的大型研究事業に代表として採択され、会話AIエージェントの社会実装と国際的な標準化を主導している。研究成果の社会実装を加速するため、2022年に株式会社エキュメノポリスを共同創業。「Towards Human-AI Co-Evolving Society(人とAIの共進化社会の創出)」を掲げ、会話AIを用いたスピーキング診断サービス「LANGX Speaking」を公教育および言語テスト領域へ展開している。JEITAベンチャー賞、大学発ベンチャー表彰(科学技術振興機構理事長賞)、SIGDIAL Best Paper Award、Interspeech Best Student Paper Award、SXSW EDU Finalist、東洋経済「すごいベンチャー100」など、学術と事業の両面で国内外から評価を受ける。専門は会話AIエージェント、社会言語学、ヒューマン–AIインタラクション。
田中 克明(株式会社amulapo 代表取締役CEO)

宇宙ロボットの専門家、博士(工学)。早稲田大学先進理工学研究科では、高西淳夫研究室にて主にフィールドロボットの研究(屋外調査用自律移動型ロボットの不整地移動性)を実施。在学中に開発した不整地移動ロボットが製品化し、大手通信企業に4台販売した。在学中に、文科省リーディングプログラム、EDGEプログラムなどを経験し、イタリアの研究機関Biorobotics InstitueにてsubCULTron(国際プロジェクト)、企業インターンとして月面探査レースHAKUTOに携わる。修了後は専門性を活かし、(株)ispaceで月面探査車のモビリティの開発に従事。その後(株)amulapoの代表取締役としてxR、ロボット、AI等のICT技術を用いた宇宙コンテンツの開発に従事。宇宙をはじめとした科学技術の発展に向けて、科学技術の発信、社会実装や人材育成のための仕組みづくりに取り組む。
丸山 祐丞(EAGLYS株式会社 CSO)

2009年早稲田大学スポーツ科学学術院スポーツ医科学科卒業、2011年同修士課程修了、2016年博士(スポーツ科学)取得。2016年より早稲田大学ナノライフ創新研究機構次席研究員として文部科学省「グローバルアントレプレナー育成促進事業(EDGEプログラム)」、「次世代アントレプレナー育成事業(EDGE-NEXT」に関り、早稲田大学非常勤講師。2016年共同創業者としてEAGLYS株式会社を設立し、2018年より取締役CSOに就任。専門はバイオメカニクス、機械学習の応用、プライバシー保護機械学習。
武笠 陽介(株式会社Quanmatic代表取締役CTO)

早稲田大学大学院基幹理工学研究科情報理工・情報通信専攻修了(戸川研究室)。元DeNAソフトウェアエンジニア。学生時代に情報処理推進機構(IPA)未踏ターゲット事業に2年連続採択され、アニーリングマシン体験学習型Webアプリ「ANCAR」を開発。企業の複雑なビジネス課題を量子計算技術で解決し、産業の高度化に貢献することを目指し、2022年10月に創業メンバーの一人としてQuanmaticを立ち上げ、CPO(最高製品責任者)に就任。量子・AI・古典計算を融合した独自アルゴリズムの設計・実装に強みを持ち、ハードウェアに依存しない実用的な最適化ソリューションを提供。現在は代表取締役CTOとして、Quanmaticの経営と技術戦略を牽引し、量子技術の社会実装を加速している。
平野 梨伊(グラフェナリー株式会社 代表取締役社長)
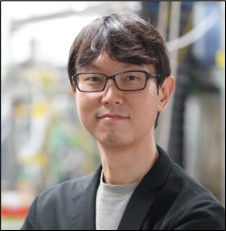
慶應義塾大学で博士課程修了後に三菱電機株式会社にて液晶ディスプレイや携帯電話基地局向けの半導体トランジスタの研究開発に従事し、担当したデバイスの上市に成功し所長表彰を複数受賞。また、海外企業と協力した新規事業の開発をプロジェクトリーダーとして牽引。社内における研究開発の戦略立案やポートフォリオ策定に従事。また、文部科学省に出向し、競争的研究資金制度の企画・運営に参画し、100億円以上の予算獲得。東北大学ベンチャーパートナーズにてディープテック投資を担当し、大学発スタートアップをスタートアップを支援。2025年から慶應義塾大学発スタートアップであるグラフェナリー株式会社の代表取締役社長に就任し、グラフェン技術の社会実装を進める。
田中 大貴(株式会社Urth CEO/早稲田大学 建築学専攻 博士3年)

大学では、建築学を専門としつつ、文科省EDGE NEXTプログラムの一つである、早稲田大学Gap Fund Projectにおいて、2019年度の最高評価および支援を受け、株式会社Urthを起業。Urthでは、2020年より、Webメタバースシステムを構築。建築技術を活かしつつ、webメタバースの概念を生みだし、企業がメタバースをオンラインの新しいコミュニケーションツールとして活用し、事業においてインパクトがある形で活かすことを支援している。
朝日 透(早稲田大学理工学術院 教授/先進理工学部長・研究科長/グローバル科学知融合研究所 所長)

1981年都立白鴎高校卒、1986年早稲田大学理工学部応用物理学科卒業、1988年物理学及応用物理学専攻修士課程修了、1992年同専攻博士(理学)、2007年経営学修士を取得。2013年先端科学・健康医療融合研究機構 機構長、2016年ナノ・ライフ創新研究機構 副機構長、2019年早稲田大学総合研究機構 グローバル科学知融合研究所所長、2021年W-SPRINGインターンシップ・キャリア支援責任者兼ライフイノベーション審査委員長を務め、学際的研究を推進し、イノベーション人材の育成に取り組む。内閣府ムーンショット型農林水産研究開発事業目標5の「地球規模の食料問題の解決と人類の宇宙進出に向けた昆虫が支える循環型食料生産システムの開発」副プロジェクトマネージャーおよび「藻類と動物細胞を用いたサーキュラーセルカルチャーによるバイオエコノミカルな培養食料生産システム」プロジェクトメンバー、JST創造科学技術推進事業(ERATO)「山内物質空間テクトニクスプロジェクト」プロジェクトマネージャー、尾道市ウェルビーイング政策アドバイザー。「サスティナブルな未来食の普及に向けた産官学共創コンソーシアム」会長を務める。専門はキラル科学、生物物性科学、結晶光学、機能性薄膜、対称性の破れ、循環型食料生産システムの研究。
【司会】
野中 朋美(早稲田大学理工学術院 創造理工学部 教授/「ECLSS環境における人間の快適性を支える製品・サービスデザイン人材育成プログラム」 研究代表者)
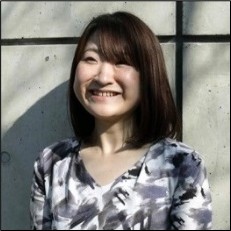
専門は経営システム工学、サービス工学。博士(システムエンジニアリング学)。慶應義塾大学環境情報学部卒業、企業で検索エンジンマーケティングに従事した後、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科(SDM)修士課程・博士後期課程に1期生として入学し4年間で早期修了。SDMでは、デルフト工科大学やスイス連邦工科大学への研究科派遣留学や、MITに研究インターンシップ滞在。神戸大学大学院システム情報学研究科特命助教、青山学院大学理工学部経営システム工学科助教、立命館大学食マネジメント学部准教授・立命館EDGE+R副総括責任者などを経て2023年4月より早稲田大学創造理工学部経営システム工学科教授。持続可能なビジネス・社会システム研究、一般民間人宇宙滞在のための宇宙QOL研究開発、働きがいや生産性などの人の情報を起点としたサービス生産システム設計に従事。文部科学省国立研究開発法人審議会臨時委員(宇宙航空研究開発機構部会)、内閣府クールジャパン・アカデミアフォーラム構成員、尾道市ウェルビーイング政策アドバイザー、IFIP WG5.7 member、日本経営工学会理事、日本創造学会理事、サービス学会理事などを務める。
松本 綾香(早稲田大学大学院 一貫制博士課程 先進理工学専攻 2年/Beyond 2020 NEXT PROJECT幹事長)

2020年早稲田大学本庄高等学院卒業、2024年早稲田大学先進理工学部生命医科学科卒業、現在、早稲田大学生物物性科学研究室 (朝日研究室) に所属。専門は物理化学、キラル科学。現在、早稲田大学本庄高等学院で非常勤講師を務める。アントレプレナーシップの養成をミッションに掲げる学生団体Beyond 2020 NEXT PROJECTに2020年度から参加し、2022年度に総務、2023年度からは事務局長を務めたのち、2025年度より幹事長を務める。国連を支える世界こども未来会議PJ、SDGs教育カリキュラムPJ、アントレプレナーシップ教育PJメンバー。
【実行委員】
中川 鉄馬(早稲田大学総合研究機構 グローバル科学知融合研究所 主任研究員)
小野寺 航(早稲田大学大学院 先進理工学研究科 生命医科学専攻 助教)
長谷部 翔大(早稲田大学総合研究機構 グローバル科学知融合研究所 次席研究員)
青木 志穂(早稲田大学大学院 先進理工学研究科 一貫制博士課程 先進理工学専攻 3年)
深澤 亮(早稲田大学大学院 先進理工学研究科 一貫制博士課程 先進理工学専攻 3年)
宮本 竜也(早稲田大学大学院 先進理工学研究科 一貫制博士課程 先進理工学専攻 3年)
岡野 洸明(早稲田大学大学院先進理工学研究科 修士課程 ナノ理工学専攻 1年)
岩田 萌里(早稲田大学大学院 先進理工学研究科 修士課程 生命医科学専攻 1年)
Jiasheng Wang(早稲田大学大学院 修士課程 生命医科学専攻 1年)
伊達 彩純(早稲田大学 先進理工学部 生命医科学科 4年)
根津 瑚春(早稲田大学 先進理工学部 生命医科学科 4年)
Tianji ZHANG(早稲田大学 先進理工学部 生命医科学科 4年)
夏山 将道(早稲田大学 先進理工学部 生命医科学科 4年)
日置 萌花(早稲田大学 社会科学部 社会科学科 2年)
小澤 剛(立教大学 経済学部 経済政策学科 3年)
【ABOUT SHIBUYA QWS】
2019年11月1日、渋谷駅直結・直上に開業した渋谷スクランブルスクエア。SHIBUYA QWS(以下QWS)は、その15階に位置する会員制の施設です。「問うだけじゃなく、出会うだけじゃなく、生み出すだけじゃなく、世界を変えよう。」をコンセプトに掲げ、多様なバックグラウンドを持つプレイヤー達の[問い]を交差させることで、未知の価値に繋がるムーブメントを生み出すことを目指しています。
https://shibuya-qws.com/
【ご回答をいただいた個人情報を含む内容について】
いただいた個人情報は渋谷スクランブルスクエア(株)の個人情報管理規定に基づき、管理し、また、使用後は適切な方法で廃棄処分いたします。
https://shibuya-qws.com/privacy-policy
【当イベントの記載情報について】
登壇者やプログラムに関する情報については、変更や追加決定事項があり次第、随時更新をさせていただきます。





